『サイダーハウス・ルール』
The Cider House Rules
ジョン・アーヴィングが自ら原作に手を加え、ラッセ・ハルストレム監督が格調高く仕上げた作品。堕胎禁止法というルールに立ち向かう。
公開:2000 年 時間:131分
製作国:アメリカ
スタッフ
監督: ラッセ・ハルストレム
原作・脚本: ジョン・アーヴィング
『サイダーハウス・ルール』
音楽: レイチェル・ポートマン
キャスト
ホーマー・ウェルズ: トビー・マグワイア
キャンディ・ケンドール:
シャーリーズ・セロン
ウォリー・ワージントン: ポール・ラッド
ウィルバー・ラーチ: マイケル・ケイン
アーサー・ローズ: デルロイ・リンドー
ローズ・ローズ: エリカ・バドゥ
看護婦エドナ: ジェーン・アレクサンダー
看護婦アンジェラ: キャシー・ベイカー
レイ・ケンドール: J・K・シモンズ
勝手に評点:
(一見の価値はあり)

コンテンツ
あらすじ
セント・クラウズの孤児院で生まれたホーマー(トビー・マグワイア)は、父のように自分を育ててくれたラーチ院長(マイケル・ケイン)の後を継ぐべく医術を学んでいた。
しかし将来に疑問を抱き始めていた彼は、ある日若いカップル、キャンディ(シャーリーズ・セロン)とウォリー(ポール・ラッド)と共に孤児院を飛び出す。
初めて見る外の世界、初めての外の仕事。ホーマーはリンゴ農園で働き、収穫人の宿舎・サイダーハウスで暮らし始める。ほどなく軍人のウォリーは戦地へ召集され、残されたホーマーとキャンディは次第にお互いに惹かれていく。
今更レビュー(ネタバレあり)
原作はグイグイ読ませるアーヴィング
ジョン・アーヴィングによる原作は、御多分に漏れず上下巻にわたる長編小説ではあるが、多岐にわたる登場人物と細かいエピソードが積み重なって読者の記憶力や理解力を試すいつものスタイルではない。
従って読みやすいし、前半は主人公ホーマー・ウェルズ(トビー・マグワイア)が産科医助手として成長する孤児院時代、後半は若いカップルと出会った縁で外の社会に触れるリンゴ農園時代と、グイグイ引きこまれる。
◇
この原作をラッセ・ハルストレムが監督し、映画化にあたってジョン・アーヴィング自ら脚色も手掛けるという贅沢さ。
今回、実に20年ぶりに作品を観直し、また原作も再読してみたのだが、新しい発見があったり、また意外と記憶が美化されていたことに気づいたりした。
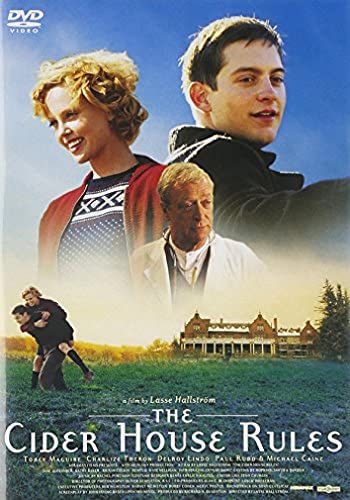
セント・クラウズの孤児院
冒頭、まだ雪の残るメイン州はセント・クラウズ(架空の町?)の駅に汽車がとまり、子供をもらい受けに夫婦が降り立つ。
前半の舞台となるこのセント・クラウズの孤児院の古い建屋が持つ懐かしく温かい雰囲気、自然に囲まれた静かな周辺環境、孤児ながらも元気に明るく暮らす子供たちと、それを支える医師ウィルバー・ラーチ(マイケル・ケイン)と二人の看護婦(ジェーン・アレクサンダー、キャシー・ベイカー)。
楽しそうな日々ではあるが、子供たちはみな、いつか自分をもらってくれる新しい両親の登場を心待ちにしている。
◇
何度も出戻ってきた挙句、もらわれ手のないホーマーは立派な若者に成長し、ろくに高校も出ていないがラーチ先生の助手経験を通じ、優秀な(勿論モグリの)産科医になっている。
今更新しい親などいらないホーマーだったが、ある日派手なコンバーチブルに乗って颯爽と孤児院に現れた若いカップル、キャンディ(シャーリーズ・セロン)とウォリー(ポール・ラッド)と親しくなり、外の世界を見てみたくなる。
そして彼は住み慣れた孤児院に別れを告げ、ウォリーの実家が経営するリンゴ農園で働かせてもらう。
舞台がリンゴ農園に移るまでの流れはざっとこんな所だが、ホーマーが初めてみる外の世界には、光あふれる海が広がり、緑の樹々の中に真っ赤に熟したリンゴが実り、孤児院にはなかった鮮やかな色彩が映える。
美しい自然とそこに暮らす人々の撮り方はいかにもラッセ・ハルストレム監督らしく、彼の代表作のひとつ『ギルバート・グレイプ』を思い出させる。
また、全編に流れるレイチェル・ポートマンの静謐で美しいテーマ曲のおかげもあり、本作はとても格調が高い作品になっている。
原作を読んで感じる物足りなさ
そこまではいい。私がどうにもしっくりきていないのは、原作との差異からくる不足感だ。勿論、大長編を二時間ちょっとの枠に収めるためには大胆な切り捨て作業が不可避であり、多少の物足りなさは仕方ない。
物語としての破綻もないし、何より原作者本人が手を加えていて、おまけにジョン・アーヴィングは脚色賞でオスカーまでもらっているのだ。どこに文句のつける余地があるよ、と言われそうなのは承知している。
長篇の原作の中で、主人公の成長譚を省略して一気に子供時代から若者にしてしまうのは、全く問題ない。アーヴィング原作映画化の『ガープの世界』で、ガープ少年が突如ロビン・ウィリアムス(大学生役、老けすぎ)になっていたくらいだから、トビー・マグワイアに違和感はない。
ただ、孤児院の女子寮にいた幼馴染の暴力的な娘・メロニィが、映画には登場しない。メアリー・アグネス(パス・デ・ラ・ウエルタ)という、ホーマーに秘かに好意を寄せる女の子は残しているのに。
メロニィは重要かつ魅力的なキャラだっただけに、この切り捨ては残念。ついでにいえば、メアリー・アグネスの存在も映画では埋もれてしまっている。
◇
ホーマーがともにリンゴ農園で働くミスター・ローズ(デルロイ・リンドー)たちが暮らすサイダーハウスの小屋。これも映画撮影用のためか小ざっぱりと綺麗すぎる印象。
こんなところに人が住むのかというような小屋にしないと、黒人労働者の扱いの格差がはっきりしない。
また、ハウスの屋上にあがってホーマーが黒人たちと酒を飲んで遠くの観覧車を眺める場面は、地形的に採用が難しかったのかもしれないが、規則を破る象徴的かつ美しいシーンだっただけに、観てみたかった。ハウスの屋上はあるのに、うまく活用できていない。
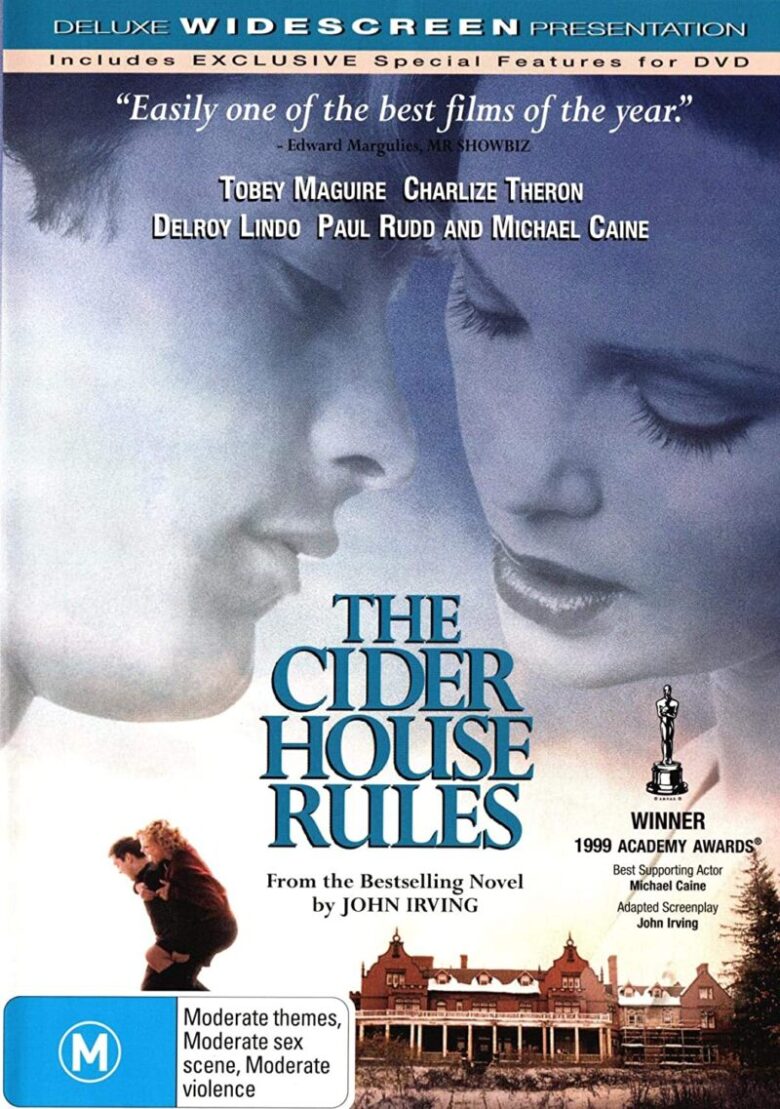
3時間枠なら実現できたか
最後にして最大の不足感は、ホーマーとキャンディ、そしてウォリーの関係描写だろう。
映画だけを見れば、親切にしてくれたウォリーが従軍してビルマ上空で日本兵と戦っている間に、ホーマーはその婚約者キャンディといい仲になっている。
そこに罪悪感はあるけれど、下半身不随となって戻ってくるウォリーと入れ違いで、彼とは顔も合わさずに、ホーマーはキャンディと別れて去っていく。そういうほろ苦い青春恋愛映画になっている。
◇
だが、原作ではホーマーはもっといいヤツで、もっと苦悩する。彼はウォリーも(友として)愛しているから。
戦死したと報告を受けたウォリーが生きていたと分かる時間差も効果的な要素だったし、ホーマーがキャンディとの間にできた子供を(ウォリーに悟られぬよう)孤児として育てることにし、その後三人(そして子供)がともに生活するという展開は、とても重要なものだと思う。
ここまで含めたら三時間超の大作になってしまうので断念したのは理解できるけど、やっぱり原作比では物足りないのだ。ああ、ないものねだり。
キャスティングについて
キャスティングは最高だったと思う。まじめそうな好青年ホーマーのトビー・マグワイアも、迷える妊婦の救済のためにホーマーを後継者にしようと画策するラーチのマイケル・ケインも、原作イメージ通りの配役だった。
三角関係に揺れ動く女心のキャンディのシャーリーズ・セロンや、季節労働者を自分のルールで管理する強面のミスター・ローズ役デルロイ・リンドーもいい。
◇
ここまでの俳優陣は覚えていたのだが、今回、ウォリーに『アントマン』のポール・ラッド、そしてキャンディの父親のエビ漁師レイに『セッション』のJ・K・シモンズが出ていたことは、初めて認識した。
今にして思えば、サム・ライミ版スパイダーマンに出ていたマグワイアとシモンズに、アントマンまで加わっていた訳だ。
サイダーハウスのルールとは
米国の妊娠中絶の合法化は1973年のことであるが、最近でも『17歳の瞳に映る世界』にあるように、合法化されたところで、中絶の悩みが綺麗に解消している訳ではない。
望まれない妊娠をした女性の駆け込み寺として孤児院のラーチ先生は当時貴重な存在だった。
自分は堕胎の手伝いはしないと言い切っていた若者ホーマーも、社会に出て、望まぬ妊娠で中絶が必要な女性を目の当たりにし、<人の役にたて>という先生の教えを思い出し、もう一度セント・クラウズに戻ってくる。
なお、終盤に登場する駅のシーンでは、ジョン・アーヴィングが駅員でカメオ出演しているそうだ。
サイダーハウスに貼られていた<べからず集>のルールは、文盲の黒人労働者には読めず、またその内容も実態を知らないものが作った、ただの押しつけだった。
そこに暮らす者には、自分たちのルールがあり、それに従って生きている。それがたとえ、ナイフによる暴力的な抑制だったとしても。身をもってそれを教えてくれたのはミスター・ローズだった。
彼は自分の娘(エリカ・バドゥ)を妊娠させ、その中絶の代償として、娘に刺されたうえで自死を選んだ。これも彼なりのルールだった。
◇
ならば、自分にも、故郷セント・クラウズのルールがあるはずだ。堕胎禁止法は、サイダーハウスの壁に貼られた紙きれにすぎない。自分は、ラーチ先生の作ったルールを受け継いでいこう。そうホーマーは決意したのだろう。
おやすみメインの王子たち、ニューイングランドの王たちよ!

