『フェイシズ』
Faces
ジョン・カサヴェテス監督が自己資金で撮った、36時間の男女の愛と葛藤。
公開:1968 年 時間:130分
製作国:アメリカ
スタッフ 監督・脚本: ジョン・カサヴェテス キャスト リチャード: ジョン・マーレー マリア: リン・カーリン ジーニー: ジーナ・ローランズ チェット: シーモア・カッセル フレディ: フレッド・ドレイパー ジム: ヴァル・エイヴリー フローレンス:ドロシー・ガリヴァー
勝手に評点:
(一見の価値はあり)
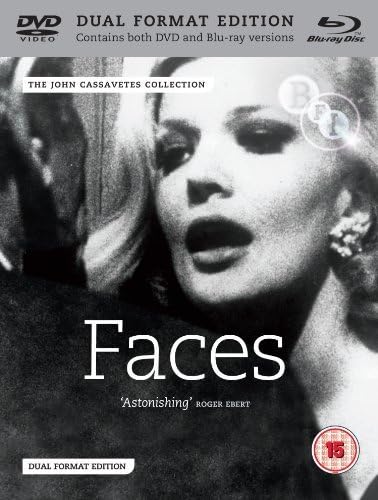
コンテンツ
あらすじ
ある日、妻のマリア(リン・カーリン)に離婚を切り出したリチャードは、高級娼婦ジーニー(ジーナ・ローランズ)と一夜を共にする。
一方、友人とディスコに出かけたマリアは、そこで出会った青年チェット(シーモア・カッセル)と関係を持つ。翌朝、罪悪感にさいなまれたマリアは睡眠薬を飲んで自殺を図るが、そこに夫リチャードが帰って来る。
今更レビュー(ネタバレあり)
冷えた夫婦の36時間が幕開け
ジョン・カサヴェテス監督が、自宅を借金のカタに入れて撮ったインディペンデント作品であり、舞台もその家が使われているという。
結婚生活14年で関係の破綻した中流階級のアメリカ人夫婦の36時間を描いている。といっても、初めからその全貌が見通せるわけではない。
◇
観る者はまず、投資保険会社の経営者である主人公リチャード(ジョン・マーレー)が仕事を終えて悪友のフレディ(フレッド・ドレイパー)とともに、高級娼館に行きジーニー(ジーナ・ローランズ)と三人でバカ騒ぎする様子を目の当たりにする。
陽気に歌い踊る男たちと、話を合わせているジーニー。
あまりに取り留めのない会話と乱痴気騒ぎに、この自由気ままなスタイルがインディペンデント映画の神髄かもと思い至る。20分近くも騒ぎが続いた頃に、フレディがジーナに「君は、いくらだ?」と切り出す。
ここで座が一気に白ける。ジーニーはリチャードとは商売抜きで親密な間柄のようだが、フレディはただの上顧客といったところか。
◇
分かりやすく、フレディは紳士的な振る舞いも遊び方も知らない下衆な成金野郎に描かれている。それに比べるとリチャードは幾分まともには見えるが、かといって女性蔑視的な態度をとる様子には大差ない。
それは、60年代という時代のマチズモのせいなのか、会社の創業社長という立場がそうさせるのか。

離婚しよう。それしかない!
リチャードがご機嫌で深夜に帰宅すると、妻のマリア(リン・カーリン)はフレディの妻ルイーズと電話中。
リチャードはそれを切らせて、夫婦の会話を始めるのだが、マリアは口に出さずとも、いかにも機嫌が悪そうな雰囲気。怒った顔が、ちょっと若い頃の鈴木保奈美っぽい。
この夫婦の会話ややりとりから、親密度合いがつかみにくいところが、とても緊張感を高める。
リチャードは強引に距離を詰めようとするが、かといってマリアの機嫌をとる訳でもなく、またマリアも笑顔と怒った顔が何度も入れ替わり、本心が読めない。
はたしてこのシーンには、シナリオがあるのか即興劇なのか、気になってしまうほどのリアルさ。そして唐突にリチャードが険しい表情で言い放つ。
「離婚しよう。それしかないだろう!」
え、それ、本気なの。マリアと同様、観る方も驚くが、どうやら本気モード。ここから、夫婦それぞれの単独行動が始まる。
インディペンデントの父
本作はインディペンデント映画でありながら、受賞は逃したもののアカデミー賞3部門(脚本賞、助演男優賞、助演女優賞)にノミネートされ、俳優ではなく監督としてのジョン・カサヴェテス監督の名をハリウッドに知らしめた。
『冬のライオン』『オリバー!』『ロミオとジュリエット』といった保守本流のハリウッド映画がしのぎを削った1969年のアカデミー賞レースで異彩を放つ。
◇
かっちりとした脚本の中でキャラクターの内面を演じきって感動を与えるのが正攻法の映画作品だとすれば、そこにスポンサーや制作会社の意向など何も忖度する必要なく、ただ純粋に撮りたいものを撮るインディペンデントの手法はキワモノかもしれない。
しかもカサヴェテス監督は内面の心理描写などに頓着せず、外形的な会話や動きだけでドラマを大胆に撮っていく。これは、21世紀の今でも新鮮味のあるスタイルに思える。60年代当時には尚更だったのではないか。

子供の頃から正攻法の商業映画を見慣れてしまった私の目には、本作は目新しくはあるが、正直いって、インディペンデント映画の傑作であると持ち上げるほどの感動はない。
これは、本作がそもそも感動をねらった映画でもないし、私が60~70年代の時代・環境に熟知していないせいもあるかもしれない。ただ、この時代に自己資金を捻出し、これだけの尖った映画を世に送り出したカサヴェテス監督の気概には、敬意を表さずにはいられない。
◇
離婚を切り出したリチャードは、緊急の要件ができたと電話をし、強引にジーニーに会いに行く。一方、残されたマリアも負けじと、有閑マダム仲間を集めて、みんなで夜の町に繰り出す。
夫婦それぞれの火遊び
ジーニーは娼館で、客のジム(ヴァル・エイヴリー)たちを相手にしていたが、そこにリチャードが参入する。
娼婦の取り合いで男たちの喧嘩になるのかと思えば、ともにビジネス界ではそれなりに立場も見識もある者同士、不思議と意気投合してくる様子が面白い。小粋なアメリカンジョークはひとつも面白くないけど。
やがてジムたちは去り、リチャードはジーニーと二人きりになる。そして甘い夜を共にする二人。
一方のマリアはデスパレートな妻たちとクラブで飲んで踊って。やがて一人の若者チェット(シーモア・カッセル)と親しくなり、彼をマリアの家まで連れ帰り、妻たちとみんなで飲み直す展開に。
20代前半の若さ溢れるチェットと、もはやそこまでの若さも溌剌さも失った女たちの対比。
「何で若い娘も大勢いたのに、私たちについてきたのよ」
「みんながあの店で場違いだったからさ」
若い男と遊ぶつもりだった妻たちは、次第に現実を思い出し、「夫を愛しているの」などと口にして、一人ずつ消えていき、気が付けば、マリアとチェットの二人きりに。結局、夫リチャードと同様、こちらも一夜を共にする。
チェット役のシーモア・カッセルはインディペンデント映画には欠かせない俳優。
『イン・ザ・スープ』(1992、アレクサンダー・ロックウェル監督)の印象が強く、つい彼の役がジーニーの娼館の初老の客あたりだろうと思っていたのだが、考えてみれば、当時まだまだ若いはず。
そうかチェットがシーモア・カッセルだったか。カサヴェテスの初監督作『アメリカの影』でデビューし、本作で役者の地位を確立する。

階段をはさんで二人
さて、朝になり、マリアは睡眠薬を大量摂取し自殺を図る。ここで本作は初めて、ドラマらしい派手な展開を迎える。そばにいたチェットは慌てるが、献身的に動き回り、どうにか彼女は一命を取り留める。
性欲と若さだけのただの若造なのかと思ったチェットが、きちんとマリアを愛し、彼女と向き合っている姿には驚くとともに好感。
このように優しく接し、なりふり構わず自分の世話をしてくれることなど、夫リチャードにはとても期待できないことだ。
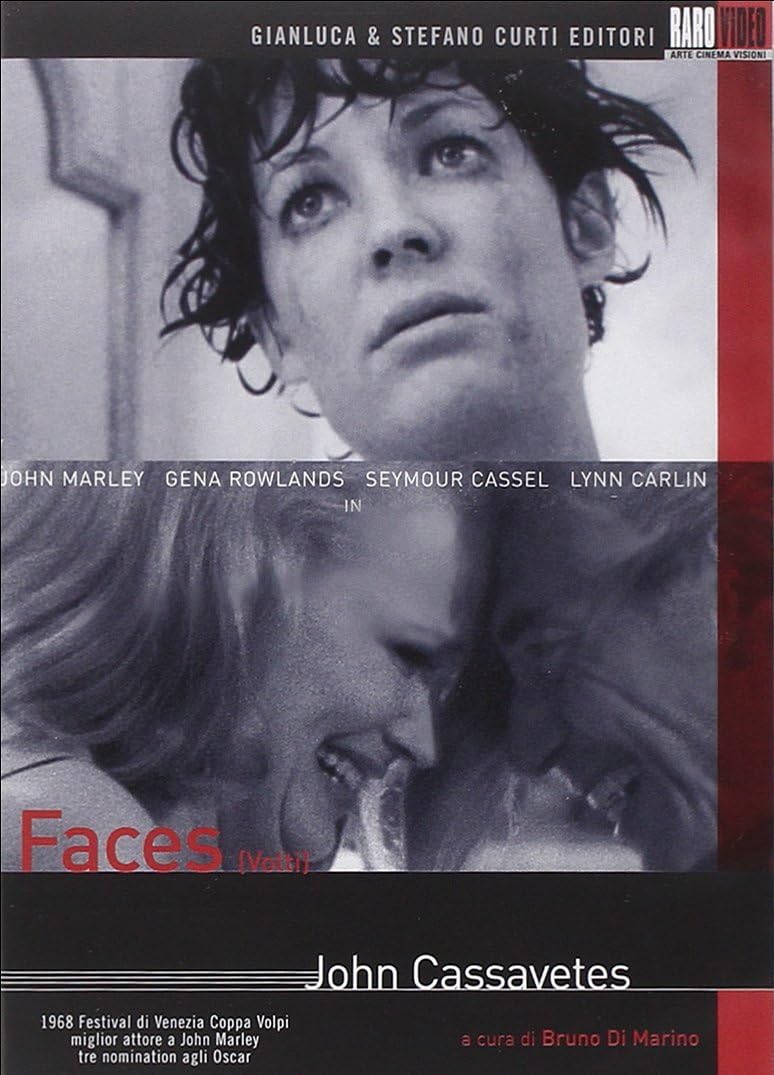
そして、その勝手な男が、陽気に朝帰りしてくる。チェットは窓から逃げて鉢合わせは免れるが、リチャードは自分の浮気を棚に上げ、妻が母子ほど年の違う若い男を引っ張り込んだことにネチネチ文句を言う。
現実逃避か自己嫌悪か、自殺未遂のマリアを夫が救って改心するならまだしも、命の恩人は若い間男だ。これだけ溝のできてしまった夫婦が、元のさやに戻るとは思えない。

それを如実に語っているのが、家の中にある階段。夫婦はそれぞれ階段の上と下に足を投げ出して座り、タバコを吸う。会話と言えば、ライターの貸し借りの台詞くらい。
ほんの数段ではあるが、夫婦の間には大きな段差があり、その溝はけして埋まらない。やがて会話もなく、二人はその場をそれぞれ立ち去っていく。
36時間あれば、夫婦に決定的な溝を作ることも埋めることもできるのだろうが、予想外な着地を見た作品であった。
