『カビリアの夜』
Le Notti di Cabiria
巨匠フェデリコ・フェリーニ監督による辛口ヒューマニズムの佳作。ジュリエッタ・マシーナが純朴な娼婦を好演。
公開:1957 年 時間:111分
製作国:イタリア
スタッフ 監督: フェデリコ・フェリーニ キャスト カビリア: ジュリエッタ・マシーナ オスカー・ドノフォリ:フランソワ・ペリエ ワンダ: フランカ・マルツィ アルベルト: アメデオ・ナザーリ 催眠術師: アルド・シルヴァーニ ジェシー: ドリアン・グレイ
勝手に評点:
(一見の価値はあり)
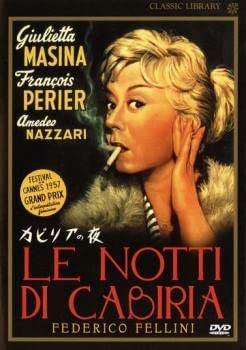
コンテンツ
あらすじ
不幸な境遇に置かれながらも、仲間に夢を語り明るく前向きに生きる娼婦カビリア(ジュリエッタ・マシーナ)。
ある夜、有名な映画俳優アルベルト(アメデオ・ナザーリ)が彼女を豪邸へ連れ帰るが、彼の元恋人が現れカビリアは追い出されてしまう。
数日後、カビリアは見世物小屋で出会った青年オスカー(フランソワ・ペリエ)に求婚されるが…。
今更レビュー(ネタバレあり)
イタリア語でまくし立てるジュリエッタの快活
『道』(1954)の大ヒットで世界的に脚光を浴びたフェデリコ・フェリーニ監督が、不評を買った『崖』(1955)に次いで撮った作品が本作。
イタリア映画なのに、なんでセビリアの夜なんだろう。フラメンコの話か?などと大きく勘違いしていた。タイトルにあるカビリアとは、ジュリエッタ・マシーナが演じる主人公の娼婦の名前だった。
◇
本作も『道』同様に、ジュリエッタ・マシーナの不思議な魅力と演技力で成り立っている作品だ。
冒頭、川辺をはしゃいで歩くカップル。だが川っぺりに立つと、突如男は女のハンドバッグを奪い川に突き落として逃亡。溺死しかけたカビリアをそばにいた者たちが救い、一命を取り留める。
だが、彼女は感謝する様子もなく、逃げ去った男を追いかけていく。
「誰だったんだ、あの女は」
「娼婦のカビリアだよ」
と子供たちが大人に教えるのが面白い。あっけらかんとしたものだ。カビリアは、貢いでいた男にカネを持ち逃げされてフラれたのだった。
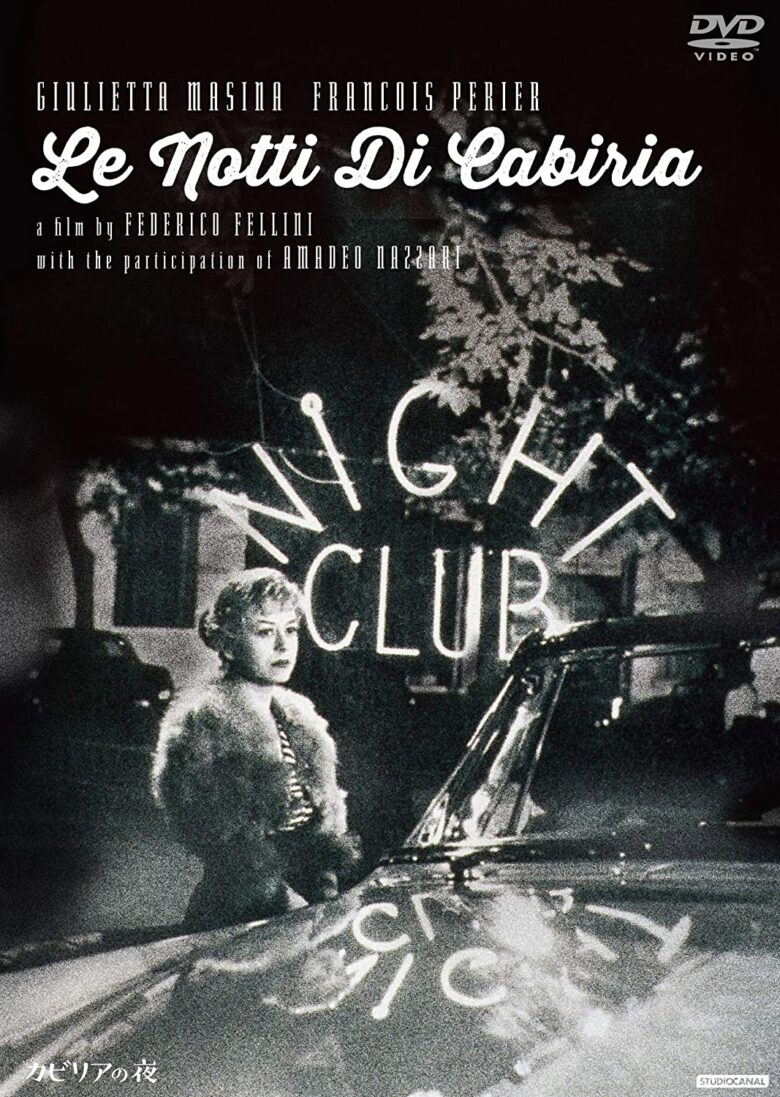
仕事仲間のワンダ(フランカ・マルツィ)に当たり散らし、結局その男のことを忘れ、再び夜の仕事に精を出すカビリア。
娼婦とはいっても、そう過激なシーンがあるわけではない。というか、濡れ場はおろか、肌を露わにするシーンさえない。
仲間の娼婦たちと夜の道路沿いの仕事場に立ちはするが、友人の男相手に浮かれてマンボを踊ったり、仲間のクルマに乗せてもらったり、刹那的ながらも楽しい日々を過ごしている。
カビリアがローンを払い終わった小さな家に住んでいるあたりも、妙に堅実で興味深い。
俳優アルベルトとの出会い
『道』でジュリエッタ・マシーナが演じた、心優しく献身的なジェルソミーナとは少々違い、口汚いし攻撃的なところもある娼婦のカビリアだが、根は純粋でお人好し。
こんな仕事をしているが、いつか愛する人と結婚して家庭を持ちたいと願っている。そんなカビリアが偶然夜の町で出会ったのは、売れっ子俳優のアルベルト(アメデオ・ナザーリ)だった。
はじめは女に命令するだけの傲慢な男にみえたが、連れていかれた高級クラブでの彼女との接し方や、招かれた大豪邸での優しいふるまいに、次第に彼女はこの俳優に惹かれていく。

だが、いい雰囲気になった夜に喧嘩別れした女ジェシー(ドリアン・グレイ)が突如アルベルトの自宅に戻ってきて、カビリアは飼い犬とともに小部屋に隠れて、ふて寝する羽目になる。
翌朝、そんな彼女にカネを払って詫びるアルベルト。商売にはなったが、どこか寂しさを感じてしまうカビリア。
◇
やがて彼女は、洞穴に暮らす貧民たちに施しを与える篤志家に出会い、次第に信仰心を高めていったのか、娼婦仲間たちと教会のミサに行き、思いもよらず、「この生活を変えたいのです!」と神にすがる。
でも、神に祈ったところで何も変わらないことを彼女は知っている。
「松葉杖のあんただって、歩けるようにならないじゃない。私は家を売り払って、新しい土地でやり直すわ」
最愛の人オスカーとの出会い
そんなカビリアが、ある晩偶然に入り込んだマジックショーの舞台で、彼女は催眠術師(アルド・シルヴァーニ)にステージに呼ばれ、術をかけられる。
こんな胡散臭いショーの催眠術などインチキだと思っていたのだが、どうやら彼女は本当に術にかかり、見えない若者オスカーを紹介され、乙女のように愛を語らう。
◇
知らぬ間に胸の内を喋らされたと文句を言うカビリアだったが、その後、客席にいたというオスカー・ドノフォリ(フランソワ・ペリエ)があなたに感動したと言い寄ってくる。
都会で会計士をしているというオスカーに、はじめは警戒していたカビリアだったが、何度かデートするうちに、次第に心を開いていく。
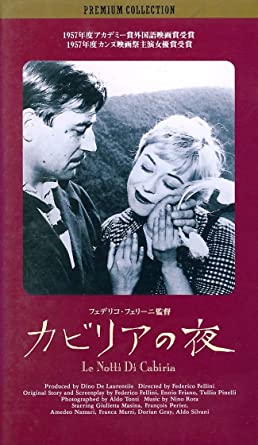
ああ、ようやく彼女も幸福に巡り合ったか。ついにはオスカーにプロポーズされる。自分の過去も今の仕事も気にしないよと言ってくれるオスカーの求婚に、舞い上がるカビリア。仕事仲間のワンダに嬉しそうに語る姿。
「ワンダ、じきにあんたにも幸せが来る。絶対よ」
そして家を売り払って、オスカーのもとへ。
◇
既に不穏なフラッグは立ちつつあったが、決定的だったのは、オスカーと二人のテラスでの食事風景。ここは私が払うわと、家を売った金をつい見せびらかすカビリア。
ああ、この善人面のオスカーもまた、カネ目当ての男だったのか。偶然にも僕の名前はオスカーなんだとか、君の過去も今の仕事も気にしないとか、全てがこのロマンス詐欺師に符合するじゃないか。
もう生きていたくない
フェリーニのヒューマニズムは、本当にどん底の状態になった人間が、最後の瞬間に抱くほんのわずかな希望を描くことで語られているように思う。
『道』のラストシーンで砂浜で悲嘆に暮れる男・ザンパノも然り、本作のカビリアもまた然りだ。
終盤、湖を見下ろす崖に立つオスカーとカビリア。逆光に髪の毛が光るカビリアが天使のように見える。河川と湖の違いはあれど、男に突き落とされそうな場面設定は変わらない。
オスカー、ホントは善人なのでは?というかすかな望みも消え失せた。まあ、彼女を突き落とさなかっただけ、良心があった男なのかも。
◇
それでも、冒頭の川辺のシーンの再来によるカビリアの心の傷は深い。家を売り払った金額だから損失が大きいということよりも、オスカーには全面的に心を許していたからだ。
「もう殺してよ。これ以上、生きていたくない!」
オスカーの前に泣き崩れるカビリア。人生とは絶望の連続なのか。これがフェリーニ流どん底の描き方。
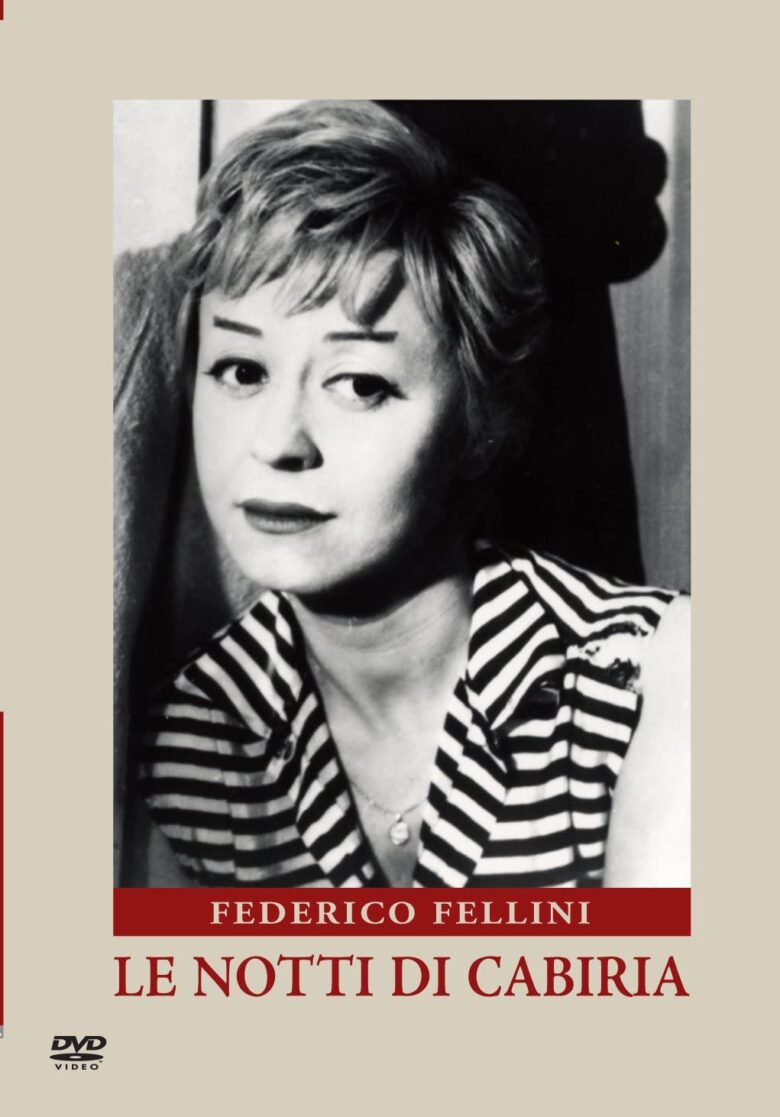
それでも生きていく
そしてラストシーン。ひとり夜の山道をとぼとぼと帰路につくカビリアに、ギターを弾く若者や踊り歩く女性、スクーター乗りなど多くの人々が寄り添うように付いてくる。まるで幻想のようだ。
カビリアは何も語らない。だが、人生に絶望し憔悴していた彼女の表情に、ラストのほんの一瞬、笑顔が戻る。泣いて崩れたマスカラの跡が、頬に道化師のような黒い涙を描く。

人生は甘くないが、それでも生きていこう。シンプルにそう語る本作は、『道』に続きアカデミー賞外国語映画賞を獲得。なお、その後フェリーニは、『8 1/2』、『フェリーニのアマルコルド』と四作でアカデミー賞外国語映画賞を、1992年にはアカデミー賞名誉賞を受賞する。
フェリーニによる辛口人生賛歌。「あんた、また男に騙されたんだねえ」とワンダが彼女を温かく迎えてくれているといいのだが。
