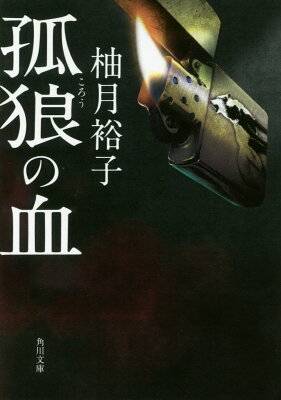『孤狼の血』
柚月裕子のベストセラー原作を白石和彌監督が映画化。東映イズムの詰まった痛快ヤクザ映画。マル暴刑事と極道の面子を賭けた闘い。
公開:2018 年 時間:125分
製作国:日本
スタッフ
監督: 白石和彌
脚本: 池上純哉
原作: 柚月裕子
『孤狼の血』
キャスト
大上章吾: 役所広司
日岡秀一: 松坂桃李
高木里佳子: 真木よう子
岡田桃子: 阿部純子
五十子正平: 石橋蓮司
吉原圭輔: 中山峻
加古村猛: 嶋田久作
野崎康介: 竹野内豊
吉田滋: 音尾琢真
苗代広行: 勝矢
上早稲二郎: 駿河太郎
尾谷憲次: 伊吹吾郎
一ノ瀬守孝: 江口洋介
永川恭二: 中村倫也
柳田タカシ: 田中偉登
友竹啓二: 矢島健一
土井秀雄: 田口トモロヲ
嵯峨大輔: 滝藤賢一
瀧井銀次: ピエール瀧
高坂隆文: 中村獅童
勝手に評点:
(オススメ!)

コンテンツ
あらすじ
昭和63年、暴力団対策法成立直前の広島・呉原で地場の暴力団・尾谷組と新たに進出してきた広島の巨大組織・五十子会系の加古村組の抗争がくすぶり始める中、加古村組関連の金融会社社員が失踪する。
所轄署に配属となった新人刑事・日岡秀一(松坂桃李)は、暴力団との癒着を噂されるベテラン刑事・大上章吾(役所広司)とともに事件の捜査にあたるが、この失踪事件を契機に尾谷組と加古村組の抗争が激化していく。
レビュー(まずはネタバレなし)
どこを切っても東映イズム
常識外れのマル暴刑事と極道のプライドを賭けた闘いに、広島大卒の新人刑事が巻き込まれる。柚月裕子の大ヒット小説を、『日本で一番悪い奴ら』の白石和彌監督が映画化。このタッグは面白い。
とても女性作家が書いたとは信じられない、<警察小説>と『仁義なき戦い』の世界の融合であるこの原作は、それ単体ですでに十分に暴力的でえげつなくて、エロい描写に満ちている。
だが、白石和彌監督の手にかかれば、更に数段、上乗せ余地があったということなのだろう。原作以上に、遠慮のない無茶な作品に仕上がった。
◇
もともとは『仁義』シリーズにインスパイアされて書かれた作品だ。数あるオファーの中から、柚月裕子が東映の企画を選んだのは当然とはいえ、その決断に感謝しなければいけない。
冒頭のいつもより古めかしい、波ザッパーンの東映三角マーク映像から、二又一成によるナレーションと暴力団幹部のスチール写真で構成された経緯説明シーン、そして全編通しての広島弁。
どこを切っても東映イズム。古い作品ではなく、今の時代でもこんな作品が撮られていることが、なんだか嬉しい。

さすが、学士さまじゃのう
暴力団との癒着を噂されるベテラン刑事・大上章吾(役所広司)、通称ガミさん。見た目は暴力団以上にそれらしく、警察官にはみえないが、暴力団にも抑えがきき、水商売関係の女性たちをはじめ、一般市民からも慕われている。
所轄に配属されてガミさんと組まされた新人刑事・日岡秀一(松坂桃李)は、大卒のインテリとからかわれ、広大(ひろだい)の愛称で呼ばれることになる。
◇
暴力、囮捜査あたりならまだしも、放火、窃盗、金品受領と違法行為何でもありの大上の捜査手法に、日岡は衝撃を受け、いちいち抵抗や是正を試みるも大上は手を緩めない。
しかも、日岡が主張する、法に則った捜査で暴力団を撲滅することが理想というのではなく、大上はあくまで、生かさず殺さずで暴力団連中をおとなしくさせる現実解を追求する。
「わしらの役目は、ヤクザが堅気に迷惑かけんよう、目を光らしとることじゃ」
この師弟の意見はまったく噛み合わないが、大上の判断軸は常に、市民の平和のため、と意外と真っ当なのだ。

暴力団の勢力図は案外と複雑
ガミさんと日岡のバディの関係は分かりやすいが、敵対する暴力団の関係は結構複雑だ。
広島の大組織である五十子会とその傘下の加古村組。五十子会の会長は五十子(石橋蓮司)、幹部には吉原(中山峻)、加古村組は組長が加古村(嶋田久作)、若頭に野崎(竹野内豊)、また構成員には吉田(音尾琢真)や関取と呼ばれる苗代(勝矢)がいる。
こいつらは、今の広島を仕切っている連中であり、顔ぶれで分かるように、本作ではヒールになる(竹野内もここでは極悪非道)。

一方の敵対組織である尾谷組は人数で劣後し、組長の尾谷(伊吹吾郎)は服役中。若頭の一ノ瀬守孝(江口洋介)が組を仕切っており、構成員は永川(中村倫也)やタカシ(田中偉登)など。
尾谷の教えを守り、義を重んじる古風な連中で、大上が肩入れしているとも噂される。五十子に戦争を仕掛けられ、報復に出ようとしている。感情移入するなら、普通こっちの組だろう。何せ伊吹吾郎だもの。

更に関係を複雑にするのが、全日本祖国救済同盟の瀧井銀次(ピエール瀧)だ。右翼団体の代表者なのだが、彼らも一応、五十子会と同じく広島仁正会という組織の一員に組み入れられており、五十子と同系のくせに大上と仲が良いという設定。
原作では瀧井は大上と幼馴染で瀧井組の組長という、映画よりはシンプルな設定だったが、それでも立ち位置はやや難解だ。
これらの組織の関係や過去の闘争経緯は、ナレーションで早口に読み上げられるだけなので、原作を読んでいても、なかなかついていけない(私だけか?)。
ただ、ピエール瀧も本作では善人顔だし、詳細が把握できなくても、俳優の顔つきで概ね敵味方の察しがつくようにはなっている。
ドギツイ演出の<豚に真珠>
ちなみに、冒頭の東映三角マークの直後に豚の鳴き声とともに登場する、経理の上早稲(駿河太郎)が勤める呉原金融は五十子会の経営するホワイト信金の傘下にある。
加古村組の連中が金づるにしていた上早稲がホワイト信金の金庫に手を付けてしまったため、バレたら五十子に殺されるとみんなで上早稲の口封じをしたわけだ。
◇
冒頭から豚の糞がアップになる映画は前代未聞だと思うが、これを食わせる拷問シーンといい、音尾琢真を全裸で監禁してイチモツに埋め込んだという自慢の真珠を摘出するシーンといい、原作にはない白石和彌監督の覚悟を感じさせる過激さだ。まさか、「豚に真珠」と洒落込んだわけではあるまいが。
台詞についても、原作から更に一歩お下劣になっている。五十子会長の「びっくり、どっきり、クリ〇〇ス」という口ぐせや、ヒロインの桃子(阿部純子)に言わせる放送禁止用語。まあ、よくやるわ、これも東映っぽさか。
◇
作品の舞台である呉原というのが架空の地名だとは気が付かなかった、いかにも広島にありそうで。昭和63年、暴力団対策法成立直前という設定もうまい。
現代に近づくほど、同じ役所広司が社会復帰に苦労する『すばらしき世界』や、同じ駿河太郎が拷問に遭わす立場になる『ヤクザと家族 The Family』のようになり、本作のような世界は描けないから。
当時のクルマや風景など、頑張って作っているのも伝わった。自販機のサントリー飲料の昔のロゴ(ぐるぐるのやつ)、懐かしかった。
レビュー(ここからネタバレ)
ここからネタバレしている部分がありますので、未見の方はご留意願います。
原作との違いは意外と多い
公開当時は、概ね原作の忠実な映画化だった印象を持っていたのだが、改めて観賞してみると、結構異なる部分が多いことに気が付く。
アレンジが上手なのか、原作にあった場面や会話を、うまく別のシーンに組み込んでいるのだ。
◇
薬局の店番をしていた桃子が、原作にはない日岡のオンナというのは分かりやすいが、原作で大上たちが常連の小料理や志乃の女将・晶子という重要なキャラは映画では割愛され、原作にもいたクラブ梨子のママ・里佳子(真木よう子)が二つの役を兼ねるような設定になっている。
繋ぎ方に不自然さはなく、時間的制約からはいいアイデアとも思える。
だが、そもそも抗争で殺された尾谷組幹部の妻であった彼女が、一人で小料理屋をやっているという原作の設定から、夫と死別して尾高組の若い組員タカシ(田中偉登)といい仲になっているママというのは、だいぶ受ける印象が違う。

妻と乳飲み子を暴力団組織に殺されたという大上の過去や、日岡が実は警察上層部から送り込まれた密偵であることのネタバラシの早さなども、原作のトーンとは随分変えているポイントだ。
映画と原作は別ものであるし、原作者としても、まったく異論がないと柚月裕子は語っている。彼女がリクエストしたのは、象徴的な小道具である、ライターの狼模様は変えてくれるなという一点のみだそうだ。
たしかに、これがないとタイトルが生きない。ジッポーが大上から日岡に手に渡ることで、必然的に主役は交代し、その意を継ぐことにもなる。ライターの授受には深い意味があるのだ。
そいうえば、『そこのみにて光輝く』での菅田将暉には、「お前から、ライターなんかもらうんじゃなかった」という台詞もあった。
なかなか練られた演出の数々
「豚に真珠」のみならず、監督こだわりの演出が随所にみられた。例えば、大上の命令でパチンコ台の前の苗代に喧嘩をふっかける日岡。手にしたアイスコーヒーを頭からかけると、苗代の持つ牛乳とまざってコーヒー牛乳になる。
パチンコ台で牛乳飲んでるヤクザもいないだろうから、これは確信犯的演出だ。白黒が混然とした世界に足を踏み入れることの暗示なのか。
◇
冒頭の首から始まり、ラストにはその首を求めた男の首が転がって終わる皮肉めいた構成も、ヤクザ社会の無間地獄を象徴しているのかもしれない。
ただ、本作のラストはちょっと解せない。尾谷組の一ノ瀬をあそこで逮捕してしまっては、大上と日岡、一ノ瀬の信頼関係が崩れてしまうのではないか。うまく次回作に繋げられるのだろうか。
とはいえ、原作目線で気になる点は多いけれど、これだけ楽しませてくれた東映らしい映画はひさしぶりだ。ついに続編が封切られると思うと、嬉しくなる。