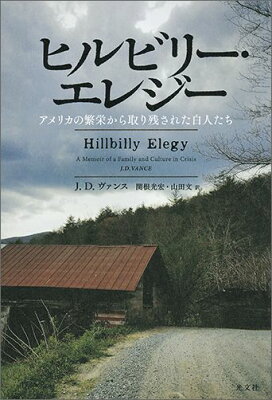『ヒルビリー・エレジー 郷愁の哀歌』
Hillbilly Elegy
米国の繁栄から取り残された白人貧民層の一家。どん底から進学しエリートを目指す息子と薬物依存の母。エイミー・アダムスとグレン・クローズのなりきり演技の迫力に圧倒。
公開:2020 年 時間:115分
製作国:アメリカ
スタッフ
監督: ロン・ハワード
脚本: ヴァネッサ・テイラー
原作: J.D.ヴァンス
「ヒルビリー・エレジー アメリカの
繁栄から取り残された白人たち」
キャスト
ベヴ: エイミー・アダムス
マモーウ: グレン・クローズ
J.D.ヴァンス:ガブリエル・バッソ
オーウェン・アスタロス
リンゼイ: ヘイリー・ベネット
ウシャ: フリーダ・ピントー
勝手に評点:
(一見の価値はあり)

コンテンツ
あらすじ
名門イェール大学に通うJ.D.ヴァンス(ガブリエル・バッソ)は、理想の職に就こうとしていたときに、家族の問題によって、記憶から消そうとしていた苦い思い出のある故郷へ戻ることを強いられる。
故郷で彼を待ち受けていたのは、薬物依存症に苦しむ母親ベヴ(エイミー・アダムス)だった。
幼いJ.D.を育ててくれた、快活で利発な祖母マモーウ(グレン・クローズ)との思い出に支えられながら、彼は自分の夢を実現するために、自分自身のルーツを受け入れなくてはならないことに気づく。
レビュー(まずはネタバレなし)
アメリカの繁栄から取り残された白人たち
J.D.ヴァンスによるニューヨーク・タイムズ紙ベストセラー第1位の回顧録「ヒルビリー・エレジー アメリカの繁栄から取り残された白人たち」を原作とした、実話に基づく物語。
◇
著者であり本作の主人公J.D.は、「ラストベルト」(錆ついた工業地帯)と呼ばれるオハイオ州の貧しい白人労働者の家に生まれ育つ。
かつて鉄鋼業で栄えた地域の荒廃、貧しい白人労働者階級の悲惨な日常を描いている。その環境から、彼自身は、海兵隊⇒オハイオ州立大学⇒イェール大学ロースクールへと這い上がっていく。
この回顧録は「トランプ支持者や分断されたアメリカの現状を理解するのに、最適の書」と評されている。
◇
原作で踏み込んでいたプアホワイトの生活にある社会問題の深さが映画化により希薄化し、ハリウッド的なお涙ありのサクセスストーリーに変わってしまった。世間的にはこのような声も多いようだ。
鑑賞時点で、私は原作を読んでいなかったのだが、興味を持ったので読んでみた。

原作を読んでみたうえで感じたこと
結論からいえば、ロン・ハワード監督の仕事はけして悪くないと思う。
確かに、映画では回顧録で書かれているよりも過剰演出気味なエピソードも散見されたし、海兵隊での厳しくも貴重な経験などもっと描かれてもよい気はする。
だが、プアホワイトの社会問題の描き方が不十分かといえば、けして原作も問題に正面から斬り込んでいる訳ではない。自分の育ってきた環境について、生々しく語ってはいるが、そこに十分踏み込めてはいない。
◇
トランプを支持する層はどんな人たちなのかを知るよい教材ではあるが、著者はそれを意図して出版した訳ではないのだろう。
そして、これは本人自身が語っていることだが、彼は育ってきた境遇の回顧録を書いただけで、世間に誇れる何かをまだ成し遂げてもいないようだ。
原作はすばらしいが、映画は冴えないという評価があったとしても、私は同意しない。
ヒルビリーにレッドネック
という訳で、ここは原作と離れて、あくまでロン・ハワード監督による家族ドラマとしてのレビューとしたい。
近年の監督の活動は、ドキュメンタリーを除けば『ダ・ヴィンチ・コード』のシリーズものや『ラッシュ/プライドと友情』『ハン・ソロ』といったスペクタクル映画が中心だ。
ベテラン監督だけに、今回も手際よく仕上げてはいるが、本作のような、派手さとは無縁のシリアスな家族ドラマは、珍しいのではないか。
◇
<ヒルビリー>とは、田舎者の意味だが、特にケンタッキー州やウエストバージニア州に住み着いたスコットアイリッシュの人々を指す蔑称らしい。
劇中に出てくる<レッドネック>は無学の白人労働者層、これも蔑称だ。
◇
J.D.の一家は、祖父母の時代にはケンタッキー州の小さな町ジャクソンの自然の中で暮らしていたが、祖母は13歳で妊娠し、祖父とともに町を出てオハイオ州のミドルタウンに移住する。
巨大な製鉄工場があり好景気に沸いた当時の勢いは今や見る影もなく、ミドルタウンの市街地は、いまやアメリカの産業の過去の栄光を示す遺物になりはてている。
このラストベルトの一角のミドルタウンで、貧困や両親の離婚、家庭内暴力、母の薬物依存症など、厳しい環境の中でどうにか成長していくJ.D.。
キャスティングについて
二人の女優の迫力溢れる演技に圧倒される。
母親ベヴを演じたエイミー・アダムス。ガラの悪いというか児童虐待に近い暴力的な母親で、薬物依存症もあるという今までの彼女にはあまりない役柄を熱演。
今なお『魔法にかけられて』のイメージが崩れない若さと美しさを維持する女優のはずだが、今回は相当振り切っている。シャーリーズ・セロンの『モンスター』並みの変貌ぶりだ(汚れた方への)。
体格も相当の迫力アップだったが、これはリアルに増量したのだろうか。
◇
祖母マモーウを演じた大女優グレン・クローズもまた、容易には本人と分からないほど、それっぽい役作りだ。品はないけど根はしっかりした老母に見えるし、娘べヴと怒鳴り合う姿もサマになっている。
孫は大手法律事務所で無学な労働階級だと一家を侮辱されるけれど、グレン・クローズはテレビドラマ『ダメージ』で法律事務所を率いていた敏腕弁護士役で有名。本来、最もエスタブリッシュ層が似合う女優なのに。
◇
主役のJ.D.は『キングス・オブ・サマー』のガブリエル・バッソ。少年時代はオーウェン・アスタロス。どちらもぽっちゃり系。
姉のリンゼイには『悪魔はいつもそこに』のヘイリー・ベネット。また、J.D.の恋人ウシャには『スラムドッグ$ミリオネア』のフリーダ・ピントー。
レビュー(ここからネタバレ)
ステップアップを阻むもの
J.D.はイェール大学のロースクールに進学し、高額な学費を捻出するために大手法律事務所のインターンの採用に応募する。
だが、折りしも重要な晩餐会の最中、田舎の母が薬物の過剰摂取で緊急入院したとリンゼイから連絡が入る。
◇
海兵隊からオハイオ州立大へ進んだだけでも、地元では夢の実現だろう。そして、J.D.は更なる高みに進みつつある。
だが、行く手を阻むものはいつも、貧しい過去の、そして家族のしがらみだ。母が薬物を断ち切れないように、負の連鎖が彼のステップアップを邪魔する。
映画は、過去と現在を慌ただしく交錯させ、J.D.は採用試験を半ばあきらめ、遠路はるばる帰省する。
◇
本作は、どん底の家族が一丸となって、息子を貧しくも健やかに育てて、また輝かしい場所を目指すことを応援する物語とはとても言えない。
英国の貧困という社会問題と家族を描いたケン・ローチ監督の『家族を想うとき』と似ているようで、そこがまるで違う。
この母親は、家族を愛してはいるが、行動や言葉はむしろ逆を行ってしまっている。どちらかといえば『Mother』で長澤まさみが演じた奔放に生きる毒親の類かもしれない。
「ダメ親だけど憎めない」の鉄板ドラマ
この母親を責めながらも、親を捨てて表舞台にのし上がっていくまでの強い思いはない。J.D.もリンゼイも、結局母親を見捨てることはできず、彼女の薬物からのリハビリをサポートする。
◇
自分の成長機会をいつも邪魔するダメな親なのだけれど、自分を愛し育ててくれたひとだから、やはり嫌いになれない。
この構図は、例えば重松清の『とんび』にも見られる、親子の絆ドラマの典型例だ。
鉄板のパターンだから、崩せないし、むしろ崩されると不快な物語になってしまう。だから、現実もそうなのだろうが、母親の更生を支えながら、息子も立派な社会人になるという展開自体に、異論はない。

ハリウッド的な仕上げにとどまったか
ただ、彼女の生き方は褒められたものではないにせよ、彼女自身も母親のマモーウの厳しい仕打ちや激しい言動を目の当たりにしながら育ってきているのだ。彼女も優秀だったし、夢もあった。
マモーウが救いの手を差し伸べなければ、J.D.だって悪友たちとドラッグ漬けの日々を過ごし、人生を棒にしていたかもしれないのだ。
◇
一個人の責めに帰するのではなく、どんなにもがいても光明がみえないヒルビリーの直面する社会問題。本作がそこに斬り込み切れていないのは、(原作もそうなのだが)やはりもどかしい。
ラストベルトの社会問題も、ハリウッドにかかれば美談になるのか。ハリウッドが白人に撮らせた『グリーンブック』は面白いが、黒人問題の本質を描ききれてはいないのと同様に。
◇
運よくJ.D.は法律事務所の仕事をつかみ、その後もエスタブリッシュメントへの階段を昇っている。また母も薬物を断てたとあれば、大きな成功例と言えるだろう。
J.D.が運と努力で勝利をつかんだのは分かったが、これを世間は、特にヒルビリーの人々はどう見るのだろう。成功者のキャリアポルノを読まされた気になるだけではないのか。
社会の構造が変わった訳でなく、ミドルタウンに暮らす多くの人々は、まだ貧困に喘いでいる。一つの家族がそこから逃げ切っただけで、ハッピーエンドとは呼べない。