『めまい』
Vertigo
アルフレッド・ヒッチコック監督の代表作に挙げられるサスペンス。高所恐怖症の元刑事が追いかける女の幻影。
公開:1958年 時間:128分
製作国:アメリカ
スタッフ 監督: アルフレッド・ヒッチコック 原作: ボワロー=ナルスジャック 『死者の中から』 キャスト ジョン・スコティ・ファーガソン: ジェームズ・スチュアート マデリン/ジュディ: キム・ノヴァク エルスター: トム・ヘルモア ミッジ: バーバラ・ベル・ゲデス
勝手に評点:
(一見の価値はあり)
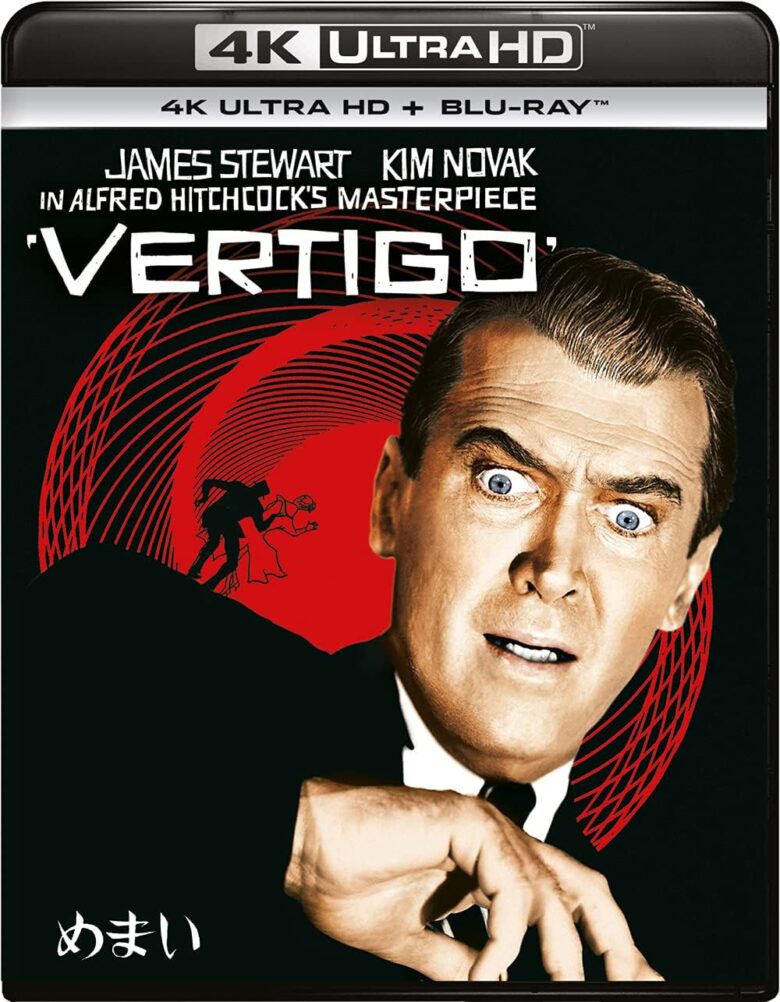
コンテンツ
あらすじ
サンフランシスコ。刑事のスコティ(ジェームズ・スチュアート)は逃走する犯人を追撃中に屋根から落ちそうになる。
自分を助けようとした同僚が誤って転落死してしまったことにショックを受けたスコティは、高いところに立つとめまいに襲われる高所恐怖症になってしまう。
そのことが原因で警察を辞めたスコティの前に、ある日、旧友のエルスター(トム・ヘルモア)が現れる。エルスターは自分の妻マデリン(キム・ノヴァク)の素行を調査してほしいと依頼。
マデリンは過去に不遇の死をとげた曾祖母カルロッタの亡霊にとり憑かれ、不審な行動を繰り返しているというのだ。
今更レビュー(まずはネタバレなし)
ヒッチコックの代表作のひとつ
アルフレッド・ヒッチコック監督の数ある監督作の中で、常にランキングの上位に入る代表作。
ジェームズ・スチュアートが演じる高所恐怖症の主人公スコティが見る“めまい”のイメージをまずは観客に浸透させ、彼が巻き込まれる高い場所でのアクシデントでスリルを増幅させる。
◇
めまいをイメージしたタイトルバックは巨匠ソール・バスによるもの。ヒッチコックとは本作が初仕事となる。
CGによるうずまきのような線画は、その後日本でも二時間サスペンスのオープニングに使われる等、すっかり時代遅れの感はあるが、公開当時は映画に初めてCGを取り入れた大変斬新なものだったに違いない。
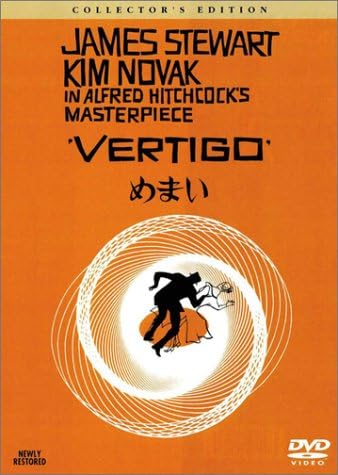
世間的には極めて評価の高い本作だが、ひねくれ者の私は、あまり本作を絶賛できずにいる。ヒッチコック自身が、本作を失敗作だと思っているという理由とはまるで異なる(彼が気に入っていないのは、主演女優なので)。
ボワロー=ナルスジャックによる原作『死者の中から』を読んだせいか、どうしてもあるギャップが気になってしまうのだ。これはネタバレになってしまうので、後述させていただく。
まずはオカルト映画の雰囲気
舞台はサンフランシスコ。映画は冒頭、刑事であるスコティが犯人を逃走中に屋根から落ちかけ、それを救おうとする同僚が転落死してしまう。
それ以来、脚立に昇っただけでもめまいがしてしまう彼が巻き込まれるサスペンス。この辺の話の運び方はさすがヒッチコック、手慣れたものだ。
高所恐怖症が理由で警察を辞するスコティ。「当分は食うには困らんよ」という優雅さだが、そんな彼に、疎遠だった旧友のエルスター(トム・ヘルモア)が声をかけてくる。
亡き義父に代わり造船業を営むエルスターが、元刑事の彼に妻マデリン(キム・ノヴァク)の素行調査を依頼するのだ。
「浮気調査など御免だ」と断りかけたスコティだが、どうやら話が違う。マデリンは曾祖母カルロッタの亡霊にとり憑かれ、不審な行動を繰り返しているという。

カルロッタの墓参りをしたり、美術館で曾祖母の肖像画をずっと眺めたり、今はホテルになっている、曾祖母のかつての部屋を借りて過ごしたり。このあたりまでは、サスペンスというよりはオカルト映画の雰囲気が濃厚。
エルスターが初めてスコティに妻マデリンを引き合わせる場面。といっても紹介するわけではなく、妻と食事をするレストランに彼を呼び寄せ、遠くから確認させるだけだが、深紅の壁紙に囲まれた店内に、グリーンのドレスのマデリンが浮かび上がって見える。
赤と緑の対比はまるで眼鏡店の検眼のようだが、この場面は印象的だ。キム・ノヴァクが輝いて見える。近年へは中国の新鋭ビー・ガン監督が『ロングデイズ・ジャーニー この夜の涯てへ』(2020)の中で、この赤と緑に強く影響を受けた映像表現をみせてくれる。

Restored Version (C)1996 Leland H. Faust, Patricia Hitchcock O’Connell & Kathleen O’Connell Fiala, Trustees under the Alfred J. Hitchcock Trust. All Rights Reserved.
ドリーズームによる<めまい>
スコティには世話を焼いてくれる、かつて恋仲だったミッジ(バーバラ・ベル・ゲデス)というガールフレンドもいるが、当然彼はヒロインであるキム・ノヴァクに次第に惹かれていく展開となる。
曾祖母に憑りつかれたように、金門橋のたもとから入水自殺を図るマデリンを海に飛び込んで救うあたりから、二人は親密な雰囲気に。
樹齢2000年のセコイアの大木の年輪をみて、「私はこのあたりで生まれ、ここで死んだのね」などと曾祖母の生きた時代を指さす、映画的なアイデアが面白い。
◇
100年前と変わらない古くからある集落にマデリンをつれていき、過去ではなく現実を直視させようとするスコティだが、うまくいかず、ついに彼女は、自暴自棄になって教会の鐘楼を駆けのぼっていく。
おいかけるスコティだが、ここで例の<めまい>が彼を襲う。被写体の大きさを変えずにズームとカメラ移動をシンクロさせる、いわゆるドリーズームという手法。これによる周辺画面の歪曲がまさにめまい状態。
大林宣彦監督の『時をかける少女』のラストショットで私はこの手法を初めて認識したのだが、本作のヒッチコックが本家本元。足元がすくわれ、もはや階段を上ってマデリンを追いかけられないスコティ。
ここから、オカルトはサスペンスに転じていく。
今更レビュー(ここからネタバレ)
ここからネタバレしている部分がありますので、未見の方はご留意ください。
馴染めなかった点
スコティの背後、鐘楼の窓の向こうをマデリンが落下していく。見下ろせば、転落死している彼女がみえる。間に合わなかった。スコティは、愛し始めていた女性を目の前で死なせてしまった。
突き落としたわけでも自殺幇助したわけでもなく、過去の不運な出来事で高所恐怖症になった元刑事が、依頼され尾行していた対象者を救えなかっただけだ。裁判は行われるが、スコティは無罪放免となる。
だが、そんなことは彼にとって何の救いにもならない。自分のふがいなさで、愛する女性を救えなかった。彼は精神を病み、しばし廃人のようになる。ここから映画は第二部に入る。
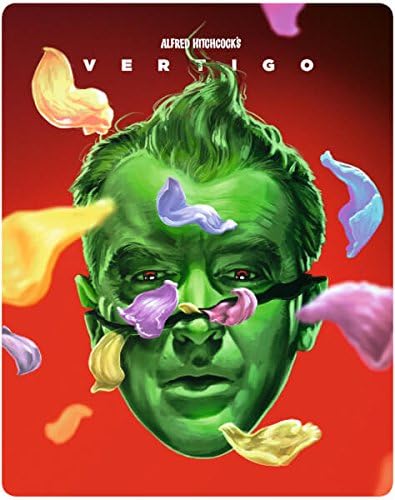
さて、先にも述べたが、原作であるボワローとナルスジャックの共作によるフランスのサスペンス『死者の中から』と本作には大きな違いがあり、私はそれに馴染めずにいる。
第二部は、死んでしまったマデリンの幻影を忘れられないスコティが、町で彼女にそっくりな女性ジュディ(キム・ノヴァク)を見かけ、執拗にアプローチする話だ。

Restored Version (C)1996 Leland H. Faust, Patricia Hitchcock O’Connell & Kathleen O’Connell Fiala, Trustees under the Alfred J. Hitchcock Trust. All Rights Reserved.
以下、ネタバレになる。死んだ恋人にそっくりな相手が現れる話は多いが、幽霊なのか、双子なのか、はたまた他人の空似なのか、いくつかあるパターンの中で、本作は実は死んでいなかったというものに該当する。
厳密に言えば、転落死したのはマデリンではなく、別人の替え玉殺人だったのだ。このオチ自体は、面白いし、原作発表当時は目新しかったのではないか。そして当然に、原作では、その真相は終盤でようやく明かされる。
だが、映画では、スコティがジュディをみかけては部屋に押しかけて強引に食事の約束を取り付ける段階で、早くも彼女の回想として、観客に種明かししてしまうのだ。
鐘楼の上で待つエルスターが本物のマデリンを転落させ、駆け上ってきた偽のマデリン(=ジュディ)は、転落をスコティに目撃させたうえで、鐘楼の上に隠れていたというわけだ。
では、なぜそんな早くにネタばらしをしたか。ジュディがマデリン本人であることを、観客は知り、スコティは知らない。その方が、彼が真相を知った時にどうなるかのハラハラ感があるはず。
サプライズよりサスペンスをヒッチコックは選んだという。これはトリュフォーとの対談集で語っていることなので、多くのレビューが引用し、だから素晴らしいのだという論調になっているように思うが、私は賛同しかねる。
だって、このジュディが何者か思いめぐらせながら、物語を追ったほうがワクワク感が強いもの。実際、私はそうだった。当時、関係者の多くはヒッチコックのこのアイデアに反対だったというが、私も彼らに同意したい。

不倫ドラマだったのか、これは
原作の舞台であるパリをサンフランシスコに変更したことは、英国人監督の米国映画という組み合わせから妥当な判断だとは思う。坂の街であるサンフランシスコと高所恐怖症を絡める面白さもあるし、街自体も絵になる。
ただ、マデリンは偽物だったとはいえ、スコティは初めから友人の人妻に我を忘れて夢中になってしまうわけだ。
たまたまその女が金目当てで夫の本妻殺しを手伝ったという真相がクローズアップされるので、不倫ものの色合いは薄れるが、犯罪の事実なかりせば、間男と人妻の歪んだ恋の話とも思える。
本来は原作のフランス文学というのが似合いなのだが、それを健康的な西海岸で、優等生イメージのジェームズ・スチュアートが演じるというのは、若干風合いが違う気はした。
ただ、監督はミスキャストというが、ヒロインに妖しい肉食系の魅力を湛えたキム・ノヴァクというのは、バランスがよかったと思う。だからこそ、代表作の一本となっているのだろう。
でも、献身的に世話してくれたガールフレンドのミッジが浮かばれないなあ。
