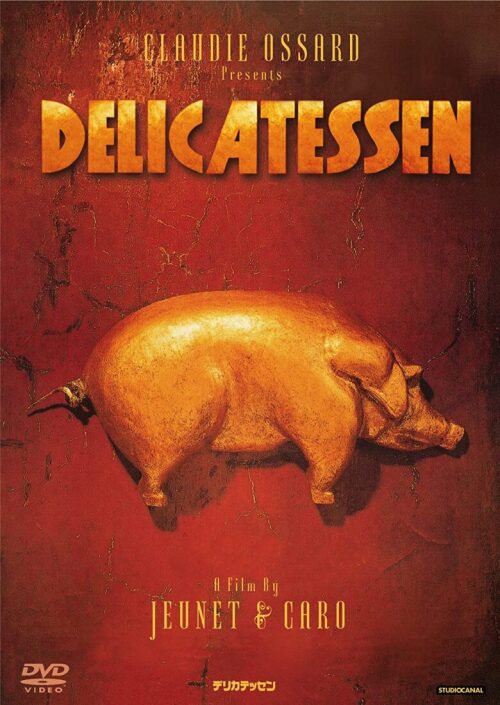『デリカテッセン』
Delicatessen
ジャン=ピエール・ジュネとマルク・キャロの長編デビュー作。肉食系の集まるアパートに現れた元ピエロの男の運命。
公開:1991 年 時間:99分
製作国:フランス
スタッフ 監督・脚本:ジャン=ピエール・ジュネ マルク・キャロ キャスト ルイゾン: ドミニク・ピノン ジュリー: マリー・ロール・ドゥニャ 肉屋: ジャン・クロード・ドレフュス プリュス: カリン・ビアール 郵便配達: チック・オルテガ マルセル・タピオカ: ティッキー・オルガド タピオカ夫人: アンヌ・マリー・ピザーニ おばあちゃん: エディス・ケール ロベール・キューブ: リュファス ロジャー: ジャック・マトゥ カエル男: ハワード・ヴァ―ノン ジョルジュ・アンテリガトール: ジャン・フランソワ・ペリエ オーロ-ル・アンテリガトール: シルヴィ・ラグナ
勝手に評点:
(一見の価値はあり)
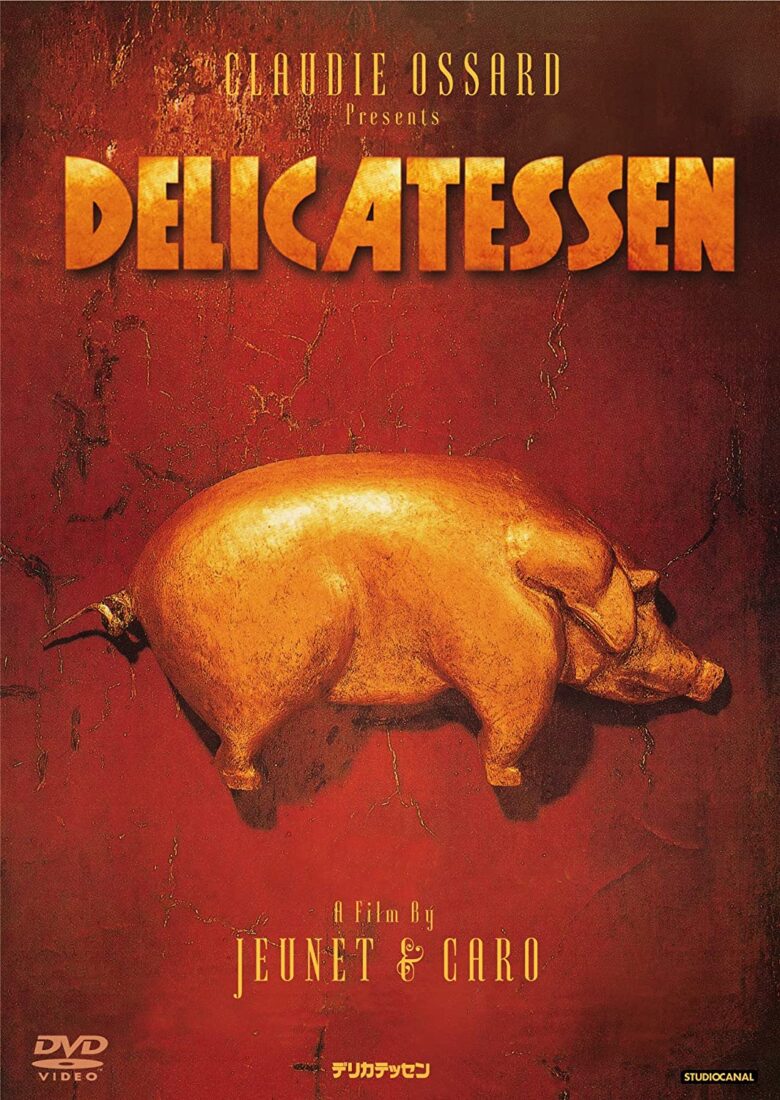
コンテンツ
あらすじ
核戦争終了15年後のパリ郊外に、ポツンと残る精肉店兼アパートのデリカテッセン。ここの住人は、いつも不気味な笑いを浮かべる親父(ジャン・クロード・ドレフュス)を始め、肉食主義の曲者揃い。
店主と住民たちは、滅多に手に入らなくなった”肉”を分け合う仲。どうも様子がおかしいこの店にある日、心優しいひとりの男(ドミニク・ピノン)が住人としてやって来る。
今更レビュー(ネタバレあり)
やっぱりジュネはフランス映画でこそ
ジャン=ピエール・ジュネ監督のブラックなユーモアたっぷりの小粋な作品。やはり、彼の魅力である独特の世界観は、フランス映画でこそ冴えるものだと改めて実感。
その点では、ハリウッドで『エイリアン4』(1997)を撮ったあとに、フランスに戻ったのは大正解だ。『アメリ』(2001)という傑作も生んだことだし。
『アメリ』からジュネの作品に入ったひとは、本作のダークな世界に驚くかもしれないが、オドレイ・トトゥの魅力に騙されているだけで、あの作品だって結構ブラックなネタが詰まっていた。

本作はジュネと共同監督のマルク・キャロの長編デビュー作。
主演は、『アメリ』は勿論、ジャン=ピエール・ジュネ監督作品にはお馴染みのドミニク・ピノン。まだ若い頃のせいか、個性的な風貌には他の作品以上にインパクトを感じる。新時代のジャン=ポール・ベルモンドの到来か。
◇
『デリカテッセン』とはいっても、フランスの洗練された肉料理が次々登場するグルメ作品のはずもなく。かといって、肉斬り包丁で血が飛び交うスプラッタ系なシーンも、直接的には出てこない。
オープニングのクレジットの出し方がハイセンスだ。例えば撮影、衣装、音楽といった役割を示す小道具に名前を書いてそれをワンカットで動き回って撮っていく。この丁寧な手作り感は、『アメリ』のオープニングでも感じたものだ。
飛んで火に入るドミニク・ピノン
冒頭、肉斬り包丁を研ぐ店主(ジャン・クロード・ドレフュス)の精肉現場を目撃した男が、ゴミバケツに隠れて逃げようとするが、惜しくも見つかってしまう。
そして翌日、肉屋の店頭に住民の客が並ぶ。どうやら食糧難で、通貨の代わりに豆の袋で取引が行われる。食糧危機に瀕しているようだ。
舞台は退廃的な近未来。とはいえ、近代的な小道具はどこにも登場せず、肉屋の上に人々が住んでいるこの建物も、相当に老朽化したアパルトマンだ。この、たまらなく懐かしい雰囲気と、青色を排除したような独特の色調が心地よい。
◇
新聞の求人広告を見て、ひとりの小男がやってくる。興行でピエロをやっていたこの男・ルイゾン(ドミニク・ピノン)を、ちょっと痩せすぎとは思ったが、店主は住み込みで採用する。
だが、怪しさ抜群のこの職場環境に、観ている者はすぐに気づく。冒頭で捕まったバケツの男は、住民たちの腹の中に納まってしまった。このルイゾンが、次の獲物になるのだと。
◇
何も知らずに不気味な館にやってきた主人公が、その地域の住民たちの餌食になってしまうパターンは、ホラー映画では割とみかけるものだ。
近年なら、『ミッドサマー』(2020、アリ・アスター監督)や『ゲット・アウト』(2017、ジョーダン・ピール監督)なんかもその類だ。
とはいえ、本作はホラーではなく、シニカルに人間愛を語るものだとすれば、同じように食い物にされてしまいそうな主人公を描いた、宮沢賢治の『注文の多い料理店』あたりを思い出させる。
奇妙な住民たち
住民たちがみな個性派揃いだ。
主人公のルイゾンの心の優しさに惹かれ、彼を救い出したいと奔走する、店主の娘ジュリー(マリー・ロール・ドゥニャ)。またも宮沢賢治を連想するが、彼女はセロ弾き。ルイゾンの鋸の刃と合わせて演奏するシーンは美しい。
◇
早くルイゾンの肉を食わせろと店主にからむタピオカ氏(ティッキー・オルガド)とその妻(アンヌ・マリー・ピザーニ)。だが、先に祖母(エディス・ケール)が犠牲になる。階段を転がる毛糸玉を地下まで拾いに行くシーンが怖い。
◇
不思議な音の缶詰を作っているロベール(リュファス)とロジャー(ジャック・マトゥ)。ロベールは規則を破り夜に部屋から出たために、片脚を店主に斬られてしまう。
彼が夢中になっている人妻オーロ-ル(シルヴィ・ラグナ)は、水道管から聞こえる囁きでノイローゼになり自殺を試みる。夫のアンテリガトール氏(ジャン・フランソワ・ペリエ)は何も知らない。老人ロベール役のリュファスは『アメリ』のちょっとズレた父親役だった。
◇
店主でありジュリーの父役のジャン・クロード・ドレフュスは、ジュネとキャロの共同次作『ロスト・チルドレン』(1995)にも、ドミニク・ピノンと共に出演。
そして店主の妖艶な愛人プリュスを演じるカリン・ビアールは、今回初めて気づいたが『エール!』(2014、オスカーに輝いた『CODAあいのうた』の元ネタ映画)で聴覚障がいの一家の妻を演じていた彼女だった。あの作品での美貌と躍動感は、本作で早くも伝わってくる。
その他、カエルに囲まれてエスカルゴ喰って暮らす老人(ハワード・ヴァーノン)やら、ジュリーに夢中の郵便配達員(チック・オルテガ)など、不思議な個性派メンバーに囲まれ、ルイゾンの運命の日は近づいていく。
肉食系VSベジタリアン
物語に変化が生じるのは、彼ら地上人が敵対視する地下政府組織トログロ団(地底人と訳されていたが)のアジトに下りて行ったジュリーが、ルイゾンを救出してほしいと交渉を持ち掛けるあたりからだ。
地上には豊富にあるトウモロコシの実を交換条件に、地底の部隊はデリカテッセンに潜入し奪還を試みる。
スパイ・アクションのような展開だが、いちいち成功するたびに手を叩き合って小躍りする団員の姿が、いかにもフランス・コメディっぽくて楽しい。
雰囲気こそあれ、終始一軒のオンボロなアパルトマンでロケを完結するあたり安普請な映画なのかと思っていたが、終盤で驚かされた。
店主たちからの脱出を試みるために、ルイゾンが部屋を密閉してプールのように水道の水を貯めていき、敵がドアを開けた瞬間に、水と共に勢いよく流れ出る。
ここの大洪水シーンは、なかなか見応えがあった。当然CGではないだろうから、この時代の手作り感は楽しい。
音楽はカルロス・ダレッシオ。『アメリ』のヤン・ティルセンの音楽もノスタルジックで叙情的だったが、本作のダレッシオのスコアも負けていない。彼の音楽のおかげで、作品の格調がワンランク引き上がる。
ルイゾンのつくるシャボン玉とも相性がいい。そもそも本作では、美しいテーマ曲に加え、ベッドのきしむスプリングの音と住民たちの生活音が重なるなど、楽しい仕掛けに満ちており、おもちゃ箱をひっくり返したような作品だ。
フランス映画の粋が、ここにある。