『あの夏、いちばん静かな海。』
北野武監督の三作目はバイオレンスから脱却し、恋人同士の台詞を排した静謐なラブストーリー。
公開:1991 年 時間:101分
製作国:日本
スタッフ
監督・脚本: 北野武
キャスト
茂: 真木蔵人
貴子: 大島弘子
サーフショップ店長: 藤原稔三
サーフショップ店員: 鍵本景子
サッカー少年: 小磯勝弥
みかん女: 窪田尚美
茂の職場の先輩: 河原さぶ
茂の上司: 芹澤名人
軽トラのおじさん: 寺島進
勝手に評点:
(悪くはないけど)

コンテンツ
あらすじ
生まれつき聴覚に障害のある青年・茂(真木蔵人)は、ゴミ回収の仕事中、捨てられたサーフボードに目を留める。茂はそれを持ち帰って修理し、同じく聾唖者の恋人・貴子(大島弘子)を連れて海へ向かう。
サーフィン初心者の茂は失敗の連続だったが、常連のサーファーたちに笑われながらも懸命に練習する。やがてサーフボードが壊れると、茂は給料日を待って新品を購入し、再び海に通い始めるのだった。
そんな茂のひたむきな姿を見たサーフショップの店長・中島(藤原稔三)は、彼にウェットスーツとサーフィン大会の出場申込書を渡す。
今更レビュー(ネタバレあり)
賛否両論ではないのか
北野武監督の三作目となる本作は、サーフィンにのめりこむ聾唖者の青年とその恋人の姿を、ひたすら静かに、無駄を排して描いたラブストーリー。バイオレンス中心だった過去作とは明らかに路線が異なる。
北野監督はすぐにまたバイオレンスの世界に戻ってしまうが、だからこそ本作こそが最高の北野作品だと称賛を惜しまない声が多い。というか、多すぎる。本当なのか、ステマなのか。
◇
確かに、キタノブルーのオリジンともいわれる青を基調にした映像は美しいし、主人公の二人の恋人は言葉が喋れないので、必然的に台詞の極めて少ない、静謐な映画になっていることから、この映画を好きだというファンがいることは理解する。
だが、賛否両論あっていいと思っていた本作に、小一時間ググったところ圧倒的多数の人が絶賛していて、否定的なレビューを書く人を探すのに苦労するほどだ。これはちょっと背筋が薄ら寒くなる状況だと感じた。
私は天邪鬼なもので
私は正直申し上げて、本作を手離しで素晴らしいと持ち上げる気にはなれない。処女作ならまだしも、既に実績も名声もある北野武監督にしては、本作で表現された<いかにも素人っぽい演技や演出>は、どこかあざとさを感じる。
- 聾唖者の恋人同士という設定が生み出す徹底した説明の排除
- その静けさを埋めるかのように聞こえる波の音と久石譲のテーマ音楽
- 淀川長治先生が生前、本作を絶賛していたこと(サイレント映画に通じるものがあるからね)
- 黒澤明監督も、ラストシーン以外は高く評価していたこと
- 桑田佳祐が監督した『稲村ジェーン』のあまりのトホホな出来栄えに触発されたこと
概ね、このようなポイントを参照して、皆さん本作をべた褒めし、最後にはお約束のように、「ラストシーンさえなければね」と結ばれるのが興味深い。
今更ながら本作初鑑賞で、何の予備知識もなく観始めたため、ゴミ収集車に乗って働くこの無口な青年は、どうして何も喋らないのだろう、と思っていた。だから静かな海というタイトルなのか。
それにしても収集車から小道具に至るまで、青いものばかりよくかき集めたものだ。
◇
真木蔵人演じるこの若者が、壊れたボードを拾ったことでサーフィンに惹かれていく。
20分も経過すると、一体いつ第一声をあげるのか楽しみになってくるが、大島弘子が演じる彼女とサーフショップに訪れるシーンで、ようやく二人とも聾唖者なのだと気づく。
この辺りまでくると、本作のスタイルやテンポみたいなものが次第に分かってきて、観やすくなってくる。聾唖者同士のラブストーリー。
まるで難病ものの陳腐なドラマのように、いたずらに感動ポルノを押し付けることなく、この二人を上にも下にも置かずに、ありのままに描こうとするスタンスは好感が持てる。
私が違和感を覚えた点
だが、それでも違和感を覚える部分がいくつかある。野暮を承知でいうが、この二人はなぜもっと手話で会話しないのだろう。聾唖者があれほどまでに手話を使わずにいるのが不自然だ。
本年のアカデミー賞の話題をさらった『コーダ あいのうた』でも『ドライブ・マイ・カー』でもいいが、聾唖の人たちの会話は手話を使い活発に交わされるものだろう。派手に動かなければ、相手に伝わらないのだから。
映画の中でもっと手話を使えば良かったと言っているわけではない。それでは話が成り立たないだろう。だが、聾唖だから無口で静かという発想には無理がある。今ならコミュ障設定とかの方がもっともらしいのかもしれない。
◇
そして、はじめのうちはあまりにサーフィンが下手で、ウェットスーツもない青年を周囲のサーファー連中やサッカー少年が馬鹿にするのだが、その演技があまりに素人っぽくて萎える。
サッカー少年は青年を見ては無理に笑い、サーファー連中は自然を装って仲間と会話するのだが、この辺は学生の自主映画レベルだった。

極めつけは、久石譲のテーマ音楽だ。とても美しい旋律で、曲自体はずっと聴いていたくなる、さすが久石譲らしい作品と思う。だが、これを繰り返し畳み掛けるように流されては、結局は感動圧力がかかっているように思える。
例えば青年がサーフボード持込ではバスに乗れず夜道を歩いて帰り、しばらくしてから、一人バスに乗る羽目になった彼女と出会うシーン。
更には、余分なシーンだと言われるエンディングの回想カットには、わざわざ転調してからのこの旋律を聴かせるのだ。音楽に頼り過ぎ。
久石譲が当初考えていたという、エリック・サティ調な曲の方が、ひょっとしたらこの作品には合っていたのかもしれない。
だが、その曲は、『その男、凶暴につき』で使ったサティのアレンジ曲に似すぎてしまうため、不採用になってしまったようだ。
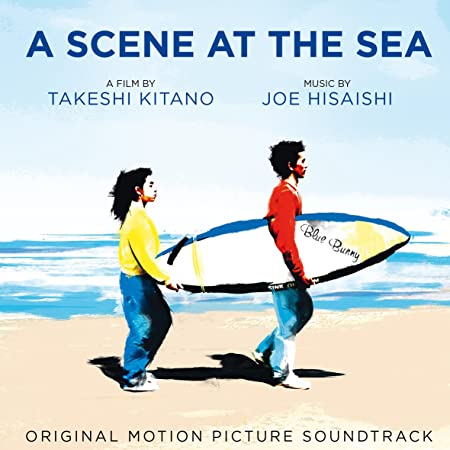
何も分かってないのか、私は
まあ、私がここに列挙したような納得いかない点は、本作を愛する方々には、「こいつ、何にも分かってねえなあ」としか思われないのだろう。それは、仕方がない。
大半の連中はこの二人と距離を置き、近づこうとしないが、なかには気のいい人たちもいる。
- はじめにちょっと高めの値でボードを売ったことに気が咎めるのか、その後何かと茂に親切にしてくれるサーフショップの店長(藤原稔三)
- 千葉のフェリー乗り場からサーフィン大会の会場まで軽トラに乗せてくれた(そして三人乗りで捕まった)親切な男(寺島進)
- ろくにゴミ収集をせずにサーフィンに明け暮れる茂を優しく見守る職場の先輩(河原さぶ)
みんな、淡泊だけれど、ちょっと優しい。この微妙なキャラ設定のトーンは北野武らしい細やかさだ。
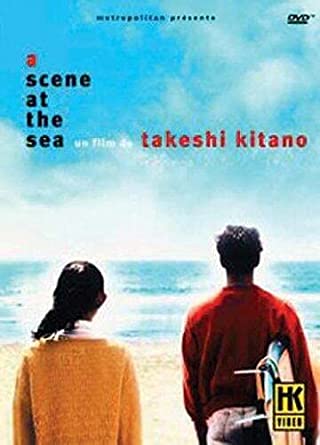
淡泊さといえば、二回も登場する千葉のサーフィン大会のシーンも、およそスポーツイベントを映画で撮っているとは思えない脱力感。サーフィンの映画なのに、主人公は勿論周囲の連中も含め、カッコよく波に乗るシーンが殆どないのだ。
茂はエントリーするも一回目は呼び出しに気づかず棄権扱い、二回目は入賞こそ果たすが、大会シーンで盛り上げようという気持ちはさらさら無い。これは人を食っていてユニークだ。
そして不可解なエンディング
北野作品の例にもれず、本作でも女性にはロクな役が与えられない(男もか)。貴子はいつも恋人の茂のそばにいるが、彼は彼女に何一つ気配りを示してはくれない。
何も文句も言わずに付き合ってくれるから、自分のサーフィンの練習の間中、砂浜で彼女を待たせているだけ。
みかん女(窪田尚美)との関係を邪推して、離れていく貴子に対して茂がやったことと言えば、家の前で石を投げて彼女の部屋の窓ガラスを割ったことだけだよ。
終盤には極めて淡泊な表現で、茂が海難事故か何かで死んでしまったことが示される。波打ち際に彼の大事なボードだけが浮いている。
やがて貴子は、ボードに二人の楽しかった頃の写真を貼り、千葉の海に行き、海に出る。海中に残されたボードは、置き去りにされたのか、彼女も海に沈んだのか分からない。
でも、それまでの、一人になってからの彼女は、笑顔をみせるようになっている。
◇
あんな勝手な男は、ボードを海に捨てて吹っ切ってやろうという明るい幕切れであってほしいが、その後に流れる映画の余韻を壊す、楽しかった日々の回想シーンをみると、吹っ切れずに後追いした説が濃厚に思える。
だから、このラストは余計なのだ。
