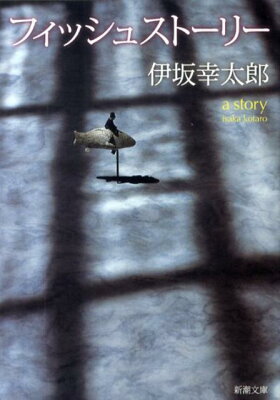『ポテチ』
伊坂幸太郎と中村義洋、そして濱田岳の黄金トリオによる、お馴染み仙台ロケの伊坂原作映画化。ちょっと今回は期待外れだったけど。
公開:2012年 時間:68分
製作国:日本
スタッフ
監督・脚本: 中村義洋
原作: 伊坂幸太郎
『ポテチ』
(『フィッシュストーリー』所収)
キャスト
今村忠司: 濱田岳
大西若葉: 木村文乃
黒澤: 大森南朋
今村弓子: 石田えり
中村親分: 中村義洋
落合修輔: 中林大樹
ミユ: 松岡茉優
尾崎選手: 阿部亮平
堂島監督: 桜金造
勝手に評点:
(私は薦めない)

コンテンツ
あらすじ
同じ年、同じ日、同じ街で生まれたプロ野球のスター選手・尾崎と、空き巣を生業とする凡人の今村が運命に翻ろうされながらも、家族や恋人を巻き込んで目に見えない強い絆によってつながれていく姿を描く。
今更レビュー(ネタバレあり)
仙台の中心でポテチを頬張る
仙台を舞台に何本も伊坂幸太郎原作の映画化で優れた作品を送り出してきた中村義洋監督。本作は、東日本大震災の復興の後押しをしたいという思いから製作された、オール仙台ロケの作品。
そういった経緯からか、あるいは原作が短編だからか、商業映画としては、68分という短い尺の作品になっている。
その辺の諸般の事情はおいておこう。復興に役立てたいという思いで作品を撮った映画作家は大勢いる。なので、ここではあくまで作品そのものに目を向けての今更レビューとしたい。
◇
これまで本サイトでは伊坂×中村タッグの原作映画化の質の高さを何度か語ってきたが、今回は残念ながら厳しい評価をせざるを得ない。というか、オール仙台ロケくらいしかセールスポイントがない。
皆勤賞の濱田岳も主演で頑張っているのだが、空回りしている。これはそもそも、映画化の題材選びで失敗しているとしか思えない。
短編では映画化には物足らないのではというつもりはない。事実、中村義洋監督の『フィッシュストーリー』は短編でも面白い。
同作は、そこに映画ならではの(音楽的な)要素を採り入れ、また、スケール不足を他の伊坂作品からエッセンスを拝借することでうまく補った映画化の成功例だ。原作越えのハイブリッド案だとさえ思った。
本作はどうだろう。もともと空き巣に入ったマンションの部屋の中での会話が中心の、動きに乏しい作品は、小説でこそ面白いが映画にする意味に乏しい。むしろ舞台の方がまだフィットするかも。
本作でも、例えば伊坂作品ではお馴染みの探偵副業の泥棒・黒澤(大森南朋)が、尾崎選手に美人局を仕掛けた若い男女(中林大樹と松岡茉優、今と雰囲気違うけど)相手に脅かす話。山形の県境の村では現代でも生贄が云々というやつだ。
あれは同じ短編集所収の『サクリファイス』に登場する<こもり様>からの着想だと思うが、どうせなら黒澤の話にとどまらず、ダイナミックに統合させてほしかった。

原作をたどっただけの映画になっている
あまりネタバレせずに語りたいとは思うが、「同じ生年月日の二人の運命は?」のキャッチコピーに尾崎選手と今村(濱田岳)の組み合わせでは、ストーリーは薄々というか、すっかり読めてしまう。
それは原作由来だから、脚本のせいではない。ただ、短編ではなく映画の根幹にかかる部分だとすると、もう少し丁寧な話の運び方でもよかったのではないかとは思う。
タイトルでもあるポテチの扱い方や台詞の意味は原作よりも相当分かりやすい。パッケージもこれ見よがしに大きい。「コンソメ味と塩味。間違ってもらって、かえってよかったかも!」
今村が落ちるリンゴを見て万有引力を発見したり、三角形の内角の総和が一定であることに自力で気づいたりするエピソードは、なにげに面白い。これは原作を知っていても楽しめた。
◇
空き巣の最中に今村が(例の有名な)野球漫画に夢中になっていて、大西若葉(木村文乃)に、「その双子の弟の方、そのうち死ぬからね」と先をバラされるエピソードが割愛されてしまった。
権利関係であきらめたのかもしれないが、この話も本作のストーリーに少なからず絡んでいるだけに残念だ。

大西若葉も今村の母親(石田えり)も、原作ではもう少し弾けて言いたい放題のキャラだったように思う。
「会っちゃおうか、出会い系、出会い系!」と、息子の彼女とこっそり会うのにはしゃぐ母に、「ステンドグラスの前でいい女って思えるのがいたら私です」と返す大西の組み合わせを期待していたが、そこまでノリノリではなかった。
◇
でも、この頃の木村文乃はすでに溌剌と輝いていて、熱烈なファンならずとも、彼女を見ているだけでこの映画の価値が見いだせるかもしれない。
怪しい男につきまとわれているミユ(松岡茉優)に「あたしたちがいじめてきてあげるから」という、のちの 『ザ・ファブル』の殺し屋にも繋がっていく頼もしさ。
◇
基本的には原作の会話を丁寧に再現しようとはしているが、それ以上でも以下でもない。となれば、他の原作とは違い、そこには世界滅亡も殺人事件も政府の陰謀もなく、ただ乾いた会話だけが残る。
伊坂幸太郎と村上春樹の映画化は、原作会話を忠実に復元しただけでは作品として成立しない。
尾崎!野球ヒーローだったんじゃねえのかよ
終盤、尾崎が代打で出場するのを期待する野球の試合観戦のシーンには、地元のボランティアの人たちが大勢参加しているらしく、いい感じの雰囲気になっている。
だが、グラウンドの野球の試合のシーンを本物らしく見せるのには、それなりの技術が必要なのだろう。さすがに、プロ野球の試合には見えないし、そう信じて観てくださいというのは、舞台でしか通用しない。
ならば、いっそ高校生の書いた戯曲から生まれた城定秀夫の映画『アルプススタンドのはしの方』の演出のように、観客席と効果音だけで、グラウンドにカメラを向けずに映画を成り立たせることもできたはずだ。
いや、むしろその方が演出効果が高かったのではないかとさえ思う。

伊坂幸太郎の作風に、感動させよう、泣かせようという演出はほとんど見かけない。本作の原作だってそうだろう。
だから、本作のラストの、尾崎がバッターボックスに入ってからの展開は、やや伊坂文学とは異なるテイストを感じた。要は、くどくてあざとい、ということだ。
◇
それを好むひともいるだろう。ただ、赤ん坊の取り違えというテーマを扱って、感動をねらいにいくのなら、是枝裕和『そして父になる』くらいの向き合い方がないと中途半端だろう。
軽め、あっさりめで最後まで撮りきったほうが、バランスがよかったように思う。
◇
エンドロールの最後の最後に、中村親分が登場してオチを持っていくとは思わなかった。この役はなんで監督自らが演じているのだろう。役名が中村だからかな。