『ガープの世界』
The World According to Garp
アーヴィングのベストセラーをジョージ・ロイ・ヒル監督が映画化。ガープをロビン・ウィリアムズが熱演。
公開:1983年 時間:136分
製作国:アメリカ
スタッフ
監督: ジョージ・ロイ・ヒル
原作: ジョン・アーヴィング
『ガープの世界』
キャスト
ガープ: ロビン・ウィリアムズ
ジェニー・フィールズ: グレン・クローズ
ロバータ・マルドゥーン:ジョン・リスゴー
ヘレン・ホルム: メアリー・ベス・ハート
エレン・ジェイムズ: アマンダ・プラマー
マイケル・ミルトン: マーク・ソーパー
クッシー: ジェニー・ライト
勝手に評点:
(一見の価値はあり)
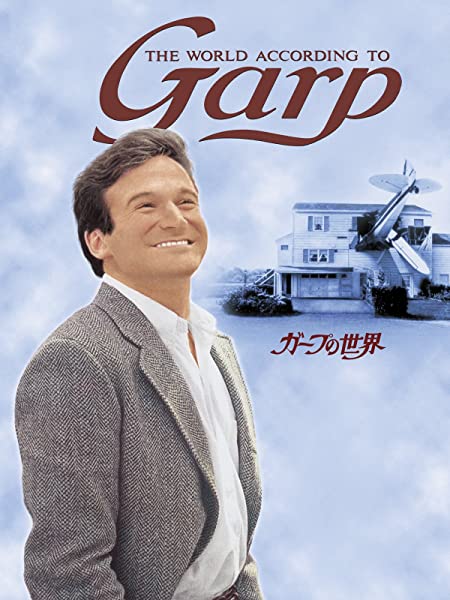
コンテンツ
あらすじ
看護婦のジェニーは、男には束縛されず子供だけが欲しいという思いから、病院に運び込まれた傷病兵と一方的にセックスする。やがて生まれた子供はガープと名づけられた。
思春期を迎えた学生ガープは、所属するレスリング部のコーチの娘ヘレンに恋をする。だがある日、ジェニーとガープは突然ニューヨークへ発ってしまう。
親子は揃って小説家を志すようになり、ジェニーはウーマン・リブのベストセラー作家となる。ガープも作家の才能が開花し、へレンと結婚。子供も授かり、順風満帆な人生を送るかにみえたのだが…。
今更レビュー(まずはネタバレなし)
アーヴィングの全てが詰まっている
この作品は実に公開時以来、何十年ぶりの鑑賞。家の書架に眠っていた、サンリオが出版した原作を読み直したら、映画も観たくなってしまった。
本作はジョン・アーヴィングの著作の初めての映画化作品にあたる。彼の小説はどの作品もよく似ているのだが、映画になると不思議とみな似ていない。どれも監督が異なるからだろうか。
その中でも一番面白いというわけではないが、最もアーヴィングらしさが詰まっている作品なのが、一大ベストセラーとなった本作ではないかと思う。
ガープという変わった名前を持つ主人公が、まさに生まれてから死ぬまでの人生を描いた一大叙事詩である。それもただの生誕とは違う。
男の肉欲を嫌悪する看護師の母ジェニー・フィールズ(グレン・クローズ)が、夫婦の関係に縛られずに子供を作るチャンスに巡り合う。
戦時中の野戦病院で、看護する瀕死の兵士がなぜか勃起を継続しているのを見て、そこに馬乗りして子供を授かったのだ。その兵士にちなんで名前はT.S.ガープと付けたが、すぐに死んだ父親の顔も素性もよく分からない。
その話を聞いていたジェニーの母親(『ドライビング Miss デイジー』のジェシカ・タンディ!)が、ショックで卒倒するのが面白い。

どこを切ってもアーヴィング印
ガープ(ロビン・ウィリアムス)は母が勤める名門男子校に住み込みで暮らすことになり、やがて成長してレスリング部に入部する。
ここから先は、キャンパスで出会ったコーチの娘のヘレン・ホルム(メアリー・ベス・ハート)と恋に落ち、やがて読書家の彼女の気を惹こうと小説を書き始め、ついにはニューヨークに移って作家としてデビューし、めでたく結婚というような流れで前半は進んでいく。
◇
何か一つでもジョン・アーヴィングの作品を読んだことのある方ならご存知のとおり、彼の作品は自伝的要素が強く、レスリング、寄宿制の名門男子校、クマのはく製、小説家、LGBT、セックスおよび性的不遇といったアイテムが頻繁に登場する。
本作も例外ではなく、ほぼフルカバーではないかと思う。原作にはクマが出てこなかったもするが、絵がではしっかりとハロウィンの仮装でクマが現れる。
◇
また、アーヴィングの小説の特徴として、大勢の登場人物が次から次へと現れて、ひとつの家族の波乱万丈のストーリーを構築し、短編を除けば殆どが、上下巻にわたる大長編小説になっている。
登場人物を覚えきれず、上巻にしかでてこない人物など訳が分からなくなってしまうことも多いのだが、なぜか最後には美しく、そして気持ちよく物語が収束する。
そして、エピローグでは、それら登場人物が最後にどうなったかを丁寧にひとりずつ紹介していくパターンが多い。これをディケンズ的で古臭いとみる読者も少なくないようだ。

そこは大御所のジョージ・ロイ・ヒル監督
これだけの大長編をコンパクトに2時間超でまとめ上げて映画にするには、それなりの技量が必要に違いないが、そこは大御所のジョージ・ロイ・ヒル監督、見事な仕上げ方だ。
思い切って割愛したキャラクターも相当数存在するし、ディケンズ的なエピローグもこの際無視ではあるが、しっかりと原作のもつ世界観は伝わってくるし、何よりテンポよく進むので、読書を挫折した人にもこれなら楽しくついていけるはず。
◇
作家として活躍していくガープは、原作では劇中で『ペンション・グリルパルツァー』や『ベンセンヘイバーの世界』といった作品を書いていき、その中身もまた楽しめる構造になっている。
これはさすがに映画では表現しきれなかったようだ。時間的な制約や、構成が複雑になりすぎるのだろう。
ただ、実際にガープが見聞きしたものから着想を得て、ニューヨークのアパートで吊り上げられたピアノを空中で演奏する男が、最後には飛び降りてしまう小説にするシーンは美しい。
また、部屋のブラインドを開くたびに、向かいのアパートでサックスを吹く男や、自分のレスリング部での練習風景などが次々と入れ替わっていく表現手法は、良く練られていた。
キャスティングについて
主人公のガープにはロビン・ウィリアムズ。高校生から30歳くらいまでの役を演じているが、特に違和感はない。いかにも人の良さそうなキャラは、彼ならではだ。
当初は、クリストファー・リーヴに来たオファーから、親友のロビンを紹介し、こういう流れになったそうだ。本作がなかったら、俳優としてのロビン・ウィリアムズは、不遇のデビュー『ポパイ』だけで終わっていたかも。スーパーマン様さまだ。
俳優としての出世作となった本作の冒頭にビートルズの<When I’m Sixty-four>が流れるが、そのロビンは惜しくも2014年に63歳で帰らぬ人となる。
◇
母親ジェニー・フィールズを演じたグレン・クローズは、映画デビュー作の本作でアカデミー助演女優賞にノミネートされている。
確かに、ジェニーのユニークなキャラや、その後映画の中でフェミニストたちに熱狂的に支持され、政治家に立候補する姿など、デビュー作とは思えない存在感がある。
実年齢で大して差のないロビンの母親も違和感なく演じきっている。ある意味、主役を完全に食っている役だ。
◇
そして、そんな彼女を支持するメンバーの一人に、ロバータ・マルドゥーン(ジョン・リスゴー)がいる。元フィラデルフィア・イーグルスのアメフト選手で今は性転換している役なので、とにかく大柄だ。
ロバータはジェニーだけでなくガープ夫妻の良き理解者となり、映画の中でも家族の一員のような役となる。

今更レビュー(ここからネタバレ)
ここからネタバレしている部分がありますので、未見および原作未読の方はご留意願います。
現代社会でも十分に通用する設定
さて、映画自体が壮大なストーリーのダイジェスト版みたいなものなので、内容については、ここでは深く語らない。
ガープの世界は、男を肉欲として嫌悪する母、性転換する前に子供を作っておくんだったと嘆くゲイ、男は敵だとして断絶している<エレン・ジェイムズ>党員など、多様性に満ちた社会を描いている。
米国では原作の読者が「ガープは実在する(I Believe in Garp)」 のワッペンを流行させたというが、本作も40年近く前の作品だというのに、まったく設定に古さを感じさせない。
◇
例えば、<エレン・ジェイムズ>党員の女性たちは、かつて男たちに輪姦され、告発できぬよう舌を切られたエレン・ジェイムズという被害者の名のもとに集結した女性運動家たちだ。
全員自ら舌を切っている過激な集団だが、実は肝心のエレン本人は、この運動に賛同していないのだ。この手の当事者を無視した活動というのは、現代にも依然横行しているように思う。
隠遁しているエレン・ジェイムズ(アマンダ・プラマー)本人が終盤に一瞬だけ登場しガープと言葉を交わすワンシーンは感動的だった。
悲惨な事故が起こるガープの世界
本作は、顔も出てこないガープの父親や祖父母のほか、反フェミニストに銃撃されて絶命してしまう母ジェニー、そして思いもよらない自動車事故で不慮の死を遂げるガープの次男ウォルト、最後には、予想外の刺客により非業の死に至るガープと、多くの葬式が続く物語でもある。
◇
特にウォルトの事故死については、住宅街で暴走するトラックの運転手に散々注意をしていたガープ自身が、夜間に無灯火で自宅車庫まで運転する<宇宙遊泳>で家族全員と妻ヘレンの浮気相手マイケル・ミルトン(マーク・ソーパー)まで悲惨な目に遭わせてしまう。
これは衝撃的だが、このような交通事故(『ドア・イン・ザ・フロア』)や偶然の積み重ね(『サイモン・バーチ』)は、アーヴィングの作品には決して珍しくない。
映画オリジナルのシーンだと思うが、最後に、ちょっと気になった点を二つだけ。
ウォルトを亡くした後、しばらく険悪だったガープ夫妻が、ようやく仲直りして寂しかったと抱きしめ合う。これはいいシーンなのだが、ここで出てくるヘレンの台詞が「また生むわ!」では、あまりに気持ちの切り替えが早すぎないか。
また、ラストにドクターヘリで緊急搬送されるガープは、あれだけ銃撃を受けたのに、酸素マスクはずして、死に際にヘレンと和やかに会話はできない。これは演出過剰だろう。
とはいえ、見応えのある作品であることに異論はないけれど。

